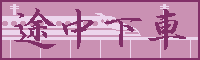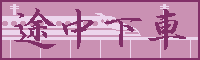|
流氷を見たくて、旅に出た。
12年前の2月、私はまだ20歳だった。学年末の試験が終わって少し暇ができたので、例の上野発の夜行急行「津軽」で出発した。当時の上野発は22時39分、青森着は翌日12時29分で、実に13時間50分をかけて悠然と走る。秋田までは夜行急行の風情もあるが、その先は単なるローカル急行に過ぎなくなる。
まだ青函トンネルの開通する前だったから、青森から連絡船に乗った。午後の便ではあり、気の毒なほどすいていた。現在のJR、当時の国鉄が、昭和50年代に入ってむやみやたらと運賃値上げをしてから、北海道に行くのにはみんな飛行機を使うようになってしまい、かつての栄光ある連絡船はすっかり寂れてしまった。私はそれまで、夏とか春とか、世間が休みの時期にばかり乗っていたので、閑散期の連絡船がこれほどすいているものだとは全く知らなかった。
連絡船は3時間50分をかけて函館に入港する。すでに冬の陽はとっぷりと暮れている。しかし、入港の風情は良かった。青函トンネルは確かに世紀の大事業だったが、開通してみれば要するにトンネルに過ぎない。退屈な暗闇が続くばかりである。絶景を誇る瀬戸大橋と較べると、地味だ。おまけに、船で刻々と北海道に近づくという味わいがすっかりなくなってしまった。
函館から「北斗」に乗った。乗車率は50%くらいだった。
22時40分に千歳空港(今の南千歳)に着いた。ここから2泊目の夜行急行「まりも3号」に乗って、流氷の見える道東へと向かう。この「まりも」も、その後特急格上げという名目で廃止された。
閑散期だが、「まりも」に乗ろうという人は結構多かった。列を作って並んでいると、
「鶴って、釧路湿原に行かないと、見られないんでしょうかね」
と、何の前触れもなく、そばに立っていた若い女が話しかけてきた。そういえばその女も、「北斗」の同じデッキから下りたのであることを私は思い出した。
「さあ、どうでしょうか」
「鶴を見に行くか、風蓮湖の白鳥を見に行くか、迷ってるんです」
「両方行くわけには行かないんですか?」
「行ってもいいんだけど、鶴の方は交通手段がなくてね」
「じゃあ風蓮湖に行けば」
「ところが、白鳥そのものは今朝大沼で見てきてしまったんで……」
その時、「まりも3号」が入線してきたので、私たちは乗り込んだ。札幌始発の列車で、すでに乗客は、席を向かい合わせにして4人分を独占したりして寝ている。女は、そういうひとりを叩き起こして、半分あけさせた。私たちは並んで坐った。
女は私と同い年であるらしかった。学生ではなく、速記タイプの研修生だという。4月から横浜地裁で働くことになっており、その前に引っ越しを口実に2週間の休みを貰ったので、北海道に出かけてきたのだそうだ。
女性には非常に珍しい鉄道マニアで、あちこち乗りまわしているらしい。おかげで、大いに話がはずんだ。
「ヨーロッパに行って、ユーレイルパスで乗りまわしてみたいんですけどね。別に新婚旅行でそうしたいというわけでもないけど……」
「新婚旅行だったらどちらをお望みですか?」
「そうね、例えば大垣行きの夜行(現在の「ムーンライトながら」)に乗って、山陰方面に鈍行を乗り継いで……」
「おおっと、そいつは大変だ」
「まあ、そこまでは言いませんけど」
彼女は笑って、
「でも、お相手は鉄道が好きな人がいいですねえ」
「鉄道好きの男ならたくさん居ますよ。あなたみたいに、女の子で鉄道好きってのは少ないけど」
「そういえば、周りを見ても、そういう女の子って、いないですね」
「女性の場合、旅行好きではあっても、鉄道好きというわけではないんだね。大体男の旅というのは、どちらかというと途中の行程を楽しむ場合が多いんだけど、そこ行くと女の旅は、目的地が絶対で、途中は退屈なだけって時が多いようですね」
「男の人でも、全然わかってくれない人も居ますけどね」
「まあ、そりゃそうだ。ぼくの友達は大体好きだけど」
「類が友を呼んでるんですね。あたしなんか全然友を呼ばなくて……いつもおひとりで旅を?」
「最近はね。前は友達とふたりのこともあったけど……3人以上になるとダメだね」
「あたしは、去年の夏に友達と旅して……それで、人と行くのはいやになっちゃったんです」
「話したいときにだけ応じてくれるような同行者がいいんですがね」
「そうそう」
女はひどく熱意を込めて言った。
「あたし、あんまり拘束されたくないし……何時間後に、どこそこで会おう、みたいな感じでできればいいんですけど」
「それやると、相手が現れないと、余計な心配をしそうだけど」
列車は漆黒の闇の中を走り続ける。一瞬過ぎていったらしい駅は、石勝高原(現在のトマム)駅だろうか。
女と肩を寄せて一晩を過ごすのも悪くなかったが、さすがに2日目の夜行となるとしんどく、帯広で他の席があいたのを幸い、移って寝た。そのまま白糠(しらぬか)あたりまで眼を醒まさなかった。
起きてみると、東の空が異様な色合いに染まっていた。どんよりとした雲の切れ目から、ミルクを溶かしこんだような白光りする空が見え、そこに鮮血の色の曙光がぐんぐん拡がってくる。地上は見渡す限りの大平原だ。あとにも先にも、これほど不気味なまでに鮮やかな夜明けは、見たことがない。
女はすでに起きていた。私が起きたのを認めると、にっこりと笑って、
「おはようございます」
と言った。
「おはようございます。すごい空の色ですね」
「ほんとに」
ふたりで、しばらく空を見ていた。
「ところで、何してるんです?」
見ると、彼女はスケッチブックをちぎっては、「くしろ」とか「ふうれんこ」とかマジックインキで大書している。
「これで停まってくれるかしら。ヒッチハイクするにしても、意思表示しないとね」
「へえ、ヒッチハイクで行くつもりなんですか」
「ええ、まあ、女の子の考えることではあるんですけどね」
確かに、私なぞが紙をかざしていても、あまり車は停まってくれそうにない。
6時12分、急行「まりも3号」は釧路に到着した。
女に別れを告げて、私は「釧路臨海鉄道」という鉄道を探しに出かけた。貨物専用の、日本最東端の私鉄である。
しばらく歩くと、レールは見つかったが、すっかり凍りついている。臨港駅らしいところがあったが、貨車が1台停まっているだけで、列車の姿はなかった。冬は使われていないのかもしれない。
一応目当てのものを見つけたので、私は莞爾として駅に戻った。
これから「しれとこ2号」で網走へ向かうつもりである。その途中で、流氷が見られるはずだ。
改札口に並んでいると、
「ハイ」
と声がした。
見ると、さっきまで一緒だった女である。
「鶴を見てきましたよ」
「えっ、もう行って来たんですか。早かったですねえ」
「そうなんです。帰りは、鶴を撮影に来ていたおじさんに載せて貰ったんで……ああ、鶴ってほんとにいいですねえ。あたし、感動しちゃった」
「それはよかった」
「これから、網走ですか?」
「そのつもりです」
「あたしは根室に行くつもりだけど……ずいぶん並んでますね。あたしも荷物とって来ようっと」
もう一度会えるとは思ってもいなかったので、不思議な気がした。まあ、このあたりから出ている列車は限られているので、それほど妙なことでもないのだが。
彼女とは、写真を一枚、一緒に撮って貰っただけで、そのまま別れた。名前も聞いていない。
ひとり旅をしていると、時々そういう友が現れることがある。しかし、ほとんどの場合、お互い名前も知らずに別れてしまう。
想い出だけが残る。
せっかく同行の士の、それも女の子が現れたのだから、そのままおつきあい願えばよかったではないかとよく言われるが、私自身はこういうあり方に満足している。
名も知らぬ、旅の友。名を知らないからこそ、想い出の点景として、いつまでも色あせずにいるのだと思うのである。
さて、いよいよ流氷列車の出発だ。
(1997.11.9..)
|