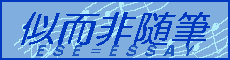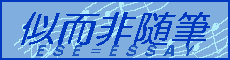|
西洋音楽が日本に入ってきたのは、明治になってからだと思っている人が多いが、決してそんなことはない。確かに一般に普及したのは明治時代、お雇い外人がやってきて学校で教え始めてからのことだが、日本人の西洋音楽との接触は、ずっと昔にさかのぼることができる。
15〜16世紀の大航海時代、西洋の文物が大量にアジアにもたらされるようになったが、その中には音楽が当然含まれていた。アフリカ大陸を大迂回しての長い航海中、音楽なしに済ませられるほど人間は強くはない。ゴアやバタヴィアなどの拠点でも、宣教師にしても商人にしても、自分たちの音楽を必要としたはずである。特に宣教師には不可欠だっただろう。教会のミサに音楽はつきものだからである。
15〜16世紀は、西洋史の上ではルネサンスの成熟期に当たる。音楽史でもルネサンス音楽というのがひとつの時代区分になっている。この時期、楽器を用いない無伴奏合唱曲が発達したが、もしかすると辺境の地で、楽器がなくても演奏できるようにという動機があったのかもしれない。
ともあれ、彼らの手によって多くの西洋音楽がもたらされたのは確実である。
ジャワのガムラン音楽は、特徴的な青銅楽器を中心とした、オーケストラと呼んでもよい華麗な合奏形態だが、その中にトランペットやオーボエを使うものがある。最近の風潮かというとそうではなく、昔から使っているという。大航海時代にヨーロッパ人が持ち込んだ楽器が取り込まれたのである。
日本だけがこうした時代の波から取り残されていたわけはない。日本を訪れた宣教師たちは、苦労して各地を布教して廻ったが、布教には教会音楽がセットになっていたことは言うまでもない。合唱隊も作られたし、オルガンなども持ち込まれたのではなかろうか。
ただ、そうしたものが、その後の日本の音楽にほとんど影響していないらしいのが不思議と言えば不思議である。キリシタンのものはなんでも禁止されたから、という単純な見方はどうかと思う。日本人という人種は、必要とあれば禁止されようがどうしようがなんでも取り入れてしまうのが常だ。
やはり、そうしたものに接した人間の絶対数が少なかったのではないかと思う。慶長時代に日本人キリシタンは75万人いたと伝えられるが、大多数は本格的なミサなど知らなかったのではなかろうか。
教会音楽だけではなく、織田信長の建造した安土城では、オペラが上演されたという話も残っている。
厳密に言えば、最古のオペラと言われるものは、1602年にカッチーニが発表した「エウリディーチェ」と考えられているので、信長では時期的に合わないが、まあオペラの前身というべき音楽劇だったのだろう。信長はこうした催しが大好きだったから、「安土公演」は充分考えられる。
こちらの方は、堺や博多などの商業都市、あるいはのちに豊臣秀吉の築いた大坂などでも上演された可能性がある。教会という密室的な空間での音楽と違って、大勢の観客が押し掛けたかもしれない。
歌舞伎の元祖と言われる出雲の阿国は、もしかするとこういうものに接して触発され、自分なりの音楽劇を創り出した……などと想像するのは非常に楽しい。日本独自の音楽劇形態である歌舞伎が、その源流において西洋の音楽劇の影響を受けていたとすれば、なんとも壮大な話である。
この時代、日本人の海外雄飛も少なくなかったから、各地で西洋音楽に接した人々も珍しくはなかっただろう。
その中で、本場の西洋音楽を耳にしたと考えられるのは、伊東マンショらのいわゆる天正少年使節や、支倉常長の使節団である。
彼らはヨーロッパで大変歓待されたそうである。ローマ法皇もイスパニア王も最上級の国賓として扱ってくれた。
当然、当時最上級とされる音楽でもてなしたに違いない。儀式の時でも、晩餐の時でも、最高の楽士たちが演奏したであろう。
そして、彼らが訪れた頃というのは、ルネサンス末期であり、音楽史上とてつもない大物が輩出した時期であった。
イタリアではパレストリーナが、北ヨーロッパではラッススが、イスパニアではビクトリアが、それぞれ脂の乗り切った頃なのである。ラッススのいた場所には行かなかったかもしれないが、パレストリーナとビクトリアには顔を合わせている可能性が充分にある。そして、彼らの作品の演奏も聴いたであろう。今の感覚から言えば、まさに垂涎としか言いようがない。
使節たちが、音楽についての記録を遺してくれなかったのが、返す返すも残念である。
徳川時代になって鎖国が行われると、当然ながら音楽も入ってこなくなったろうが、例えばロシアに漂着してペテルスブルグまで連れて行かれた大黒屋光太夫(井上靖の「おろしや国酔夢譚」の主人公)たちが、エカテリーナ2世の宮廷で、ハイドンなどの音楽を聴いたかもしれないと想像するのはロマンティックである。女帝エカテリーナはドイツの出身だから、その宮廷でドイツの音楽が好んで演奏されていたということは、それほどの無理なく考えられるのである。
幕末になると、何度も使節団が派遣されているから、西洋音楽も耳に馴染んできたかもしれない。明治になってから、日本人が比較的容易に西洋音楽に順応したのは、その前からかなり入ってきていたためではないかと思う。
1867年のパリ万国博には、徳川幕府と薩摩藩が別々にパビリオンを設けていがみ合ったことが知られているが、この会期中、会場にはヨハン・シュトラウスが楽団を率いてやって来ていた。派遣団員たちは当然、シュトラウスの生演奏を聴いたことであろう。チョンマゲを結ったサムライたちが、ウインナ・ワルツを踊ったかどうかまでは定かでない。
こういう前史があったのちに、明治を迎えるわけで、日本人と西洋音楽のつきあいは、結構長いと考えてよいのである。
明治4年(1871)、岩倉全権使節団の一員として渡欧した伊藤博文は、お雇い外人として日本に来てくれる人材探しの任務もおこなっていた。
各分野で一流の人に打診するのだが、なかなか交渉はまとまらない。一流と言われるような人間が、極東の最果ての島国などに行く気になるはずはないのである。
それでやむなく、二流以下の人に来て貰うしかなかった。実際、日本にお雇い外人としてやって来た人々の中で、世界的に高名というほどの人材は、残念ながらあまり見当たらない。
だが、音楽に関しては、もう少しで超大物が来るところだったのである。
パリに滞在中のある晩、伊藤はコンサートホールへ出かけた。
見馴れない大きな楽器の独奏会だったが、その魂をふるわすような名演奏に、伊藤は感激した。この時の伊藤の感受性は評価してよい。
伊藤は早速、この時の演奏者に、日本に来ては貰えまいかと申し出た。
この演奏者こそ、誰あろう、フランツ・リストその人だったのである。
60歳のリストは、かなり乗り気になったという。
何回か前に書いたように、リストはハンガリー生まれだが、血統的にはハンガリーの血は入っていない。マジャール語を話せたかどうかもわからない。だがそれだけに、むしろハンガリーを自分の心の故郷として感じるところが強く、「ハンガリー狂詩曲」を書き続けたことはご存じの通り。のちにバルトークらによって、リストがハンガリー土着の音楽と考えて「ハンガリー狂詩曲」のベースにしたチャルダッシュ舞曲は全然土着でなく、流れてきたジプシーの音楽に過ぎないことが判明したが、それにしてもリストのハンガリーへの愛着はまがいようがない。
ハンガリーは匈奴が西遷したと言われるフン族が建てた国であって、東洋起源であることが知られていた。当然ながら、リストの中にも、遙かな東洋への想いがあったことだろう。一度は行ってみたいと思っていたはずである。
また、宣教師に似た心情も持っていたし、山っ気の多い男でもあった。
ひとつ極東の日本へ行ってみようかという気になったとしても不思議ではない。
残念ながら、当時の60歳はすっかり老人である。本人は大いに乗り気だったようだが、健康が許さなかった。また、周囲の者たちもリストを行かせはしなかったろう。リスト招聘の議は、水に流れてしまった。
もしリストが日本に来ていたらどうだったろう。日本の音楽教育も、多少違った形になっていたかもしれない。
そしておそらく、ドヴォルザークがアメリカに招聘されて渡米し、弦楽四重奏曲「アメリカ」や交響曲「新世界より」を書いたように、リストの作品目録に「日本狂詩曲」が加わっていたのは間違いないところだろう。なんとも魅惑的な「歴史のイフ」ではあるまいか。
(1998.8.25.)
|