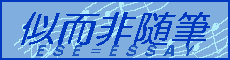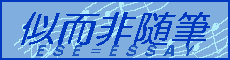|
12月に入ると、日本中あちこちでベートーヴェンの「第九」を演奏するようになる。
──師走と言えば?
という連想ゲームをすれば、昔は忠臣蔵というところだったろうが、最近では「第九」と答える人も多いのではないか。まさに日本の歳時記のひとつに数えられるほどの存在になっている。
第九交響曲というのは、9曲以上の交響曲を書いた作曲家には必ずあるわけで、ベートーヴェン特有のものではない。
しかし、日本でただ「第九」と言えば、ハイドンでもモーツァルトでもシューベルトでもドヴォルジャークでもブルックナーでもマーラーでもショスタコーヴィッチでもなく、ベートーヴェンの第九を指す。丁度、中納言の別称に過ぎない「黄門」が水戸光圀の代名詞となり、関白を引退した者の呼称である「太閤」が豊臣秀吉にのみもっぱら使われるのと同じで、ベートーヴェンの第九こそは「第九の中の第九」、「ザ・第九」というべき存在であるらしい。
ハイドンやモーツァルトは、おのおの膨大な数の交響曲を書き、第9番などはまだ初期の習作並みの作品であるので、大して重視されないのはわかる。
実は、ベートーヴェンこそ、交響曲というジャンルをこれだけ重苦しいものにした張本人であり、それゆえモーツァルトの4分の1にも満たない9曲しか完成させることができなかったわけである。その後の作曲家は、交響曲と言えばベートーヴェンを見習ったため、いずれも長大な、重苦しい作品となり、そんなものをせいぜい9曲も書けば、生命の持ち時間が尽きるようになった。
──作曲家は第9番の交響曲を書くと、じきに死ぬ。
というジンクスまで生まれ、マーラーが大変に気にしたことはよく知られている。そのため彼は第8番を書いたのちノイローゼのようになり、9番目に書いた交響曲には交響曲とは名付けず、カンタータ「大地の歌」として発表した。それで死ななかったので、大丈夫かと思って第9番を書き、それでも多少気になったのかほぼ並行して第10番も書き始めたが、やっぱり第10番の完成前に死んでしまった。「大地の歌」を素直に交響曲として発表しておけばジンクスを破れたのに、墓穴を掘ったようなものである。
このジンクスは、ショスタコーヴィッチが軽々と15曲の交響曲を書いたことによってすでに破られているので、今後の作曲家は気にしなくてよろしい。
さて、そうしたジンクスにまでなった最初のものがベートーヴェンの「第九」であった。
奇妙なのは、年末になってあちこちで演奏される「第九」のほとんどがアマチュアによる演奏であることだ。大体どこでも、6月頃に市民や区民に向けて
「あなたも“第九”を歌いませんか?」
といったような広報がなされ、普段はカラオケくらいでしか歌など歌わないお父さんたちや、それよりずっと活動的なお母さんたちが集まってくる。そして、そのあたりで無聊をかこっている音大声楽科の卒業生などをかき集めて、ヴォイス・トレーニングとドイツ語の発音練習を、ごくざっと速成でおこない、12月の本番に向けて毎週稽古するのである。
ベートーヴェンの「第九」は悠に1時間を超え、指揮者の好みによっては1時間半にも及ぶ大曲であるが、肝心の合唱が歌う部分というのはせいぜい15分足らずに過ぎない。全国の「普通の」人々が、このわずか15分足らずのために、半年前から目の色を変えて練習開場に押し掛ける有様は、異様としか言えないものがある。
「第九」は音楽的にも声楽的にも、決して易しい曲ではない。音楽的な深さについてはあとで考えるとして、純粋に声楽的な見地から見た場合でも、大変な難曲に属する作品である。
前にもこのシリーズで書いたことがあるが、ベートーヴェンは本質的に器楽的な発想の作曲家である。声楽曲にすぐれたものがあることは否定しないが、それはやはり器楽的な発想、例えばヴァイオリン曲のような発想のもとに書かれた作品なのであり、人間の声そのものから発想してゆくということは、ベートーヴェンの資質としてできなかったと言ってよい。
ましてや晩年は聴覚を失い、いよいよ観念的な音の世界に入りこむことになる。現実の歌手が歌いやすいかどうかなどということは、彼の知ったことではなかった。彼は自分の必要とする音をひたすらに書き続けたのであり、歌手の生理とか心理とかは一顧だにしなかった。
そのため、独唱合唱を問わず、「第九」は非常に歌いずらい。ベートーヴェンはこの曲で、人声をも楽器の一種として扱っているようだ。蜿蜒と続く高音、12度に及ぶとてつもない(しかも一瞬の)跳躍、とても人声の限界などに配慮しているとは思われない。
こんな難しい曲をよく歌うものだと感心する。ましてや歌詞は、ほとんどの日本人が馴染みのないドイツ語なのである。
もちろん、そうやって舞台に乗った「第九」の出来はと言えば、たいていの場合、ドイツ語もカタカナにしか聞こえないし、ハーモニーもかなり曖昧だし、なんとなくざわざわとしたままで進んでゆくのはやむを得ない。
しかし、この曲には、そういう難点を超えて、強引に人を感動させてしまうものがある。
私自身も何度か合唱にのったことがあるし、合唱指導や練習ピアノをここ15年近くずっと続けているが、この曲を歌い終えると確かに異様な達成感を覚えるのである。
──歌ったぞぉぉぉ!
と、拳を固めて天に突き上げたくなるような、妙に高揚した気分になる。ヘンデルの「メサイア」やモーツァルトの「レクイエム」を全曲歌っても、「第九」を歌い終えた時のようなハイな気分にはならない。いわば「第九マジック」としか言いようのない雰囲気があり、それに味をしめた人々が、また翌年6月頃になると稽古場に押し掛けることになるのである。
客席の方にもその高揚感が伝染して、「第九」に限っては、かなりお粗末な演奏であっても、コーダのオーケストラが鳴り終わると、なんとなくハイになってしまい、ブラヴォーが飛ぶことになる。一部の聴客はその気分に当てられ、翌年新たな参加者として合唱に加わる。どこの合唱団もメンバー集めには苦労しているが、「第九」の合唱団員ばかりは、十何年続けていても、毎年のようにかなりの新参加者があるのが常である。
一部のしたり顔の評論家や音楽愛好者などは、
「ドイツ語の意味もわからず、『第九』に込められたベートーヴェンの想いに触れることもなく、ただいい加減に盛り上がって終わる騒ぎなど、真のクラシック音楽の理解になどつながらない」
云々と苦々しげに言い、はては
「ベートーヴェンに対する冒涜である」
とまで、目尻を吊り上げて言い放ったりする。
「第九」ばかり盛り上がることについては、私もどうかと思うことが多いのだが、日本人がなぜこれほど「第九」を好むのかということについても、一応考えてみる必要があるだろう。
そのことについては、何度かテレビのドキュメンタリーなどで扱われたことがある。
また、給料の安いオーケストラの越年対策のためだという説も、業界内ではまことしやかにささやかれている。確かに、12月だけで20回以上の「第九」をこなすオケもあり、書き入れ時であることは間違いない。
が、一応、ここでは、日本における社会的な背景とかそういうことは触れず、「第九」の音楽的な面だけに即して考えるとしよう。
ベートーヴェンは、古典派の作曲家と言われている。
しかし本によっては、その後期はロマン派に属するとか書いてあることがある。
古典派とかロマン派とか言われても、それぞれがどういうものであるかをきちんと把握していないと、こう聞いても
──はあ、そうなんですか。
と言うほかない。
たいていの教科書には、こんなことが書いてある。
古典派の時代には、ホモフォニーの様式が確立されると共に、ソナタやロンド、変奏曲といった形式が重んじられ、絶対音楽がたくさん書かれた。絶対音楽というのはこの場合、標題を持たず、ソナタ第1番、弦楽四重奏曲第2番といった形でのみ呼称される曲のことを言う。
一方ロマン派の時代には、人間の感情をより重んじたため、標題音楽や性格的小品(バラード、スケルツォなど)が好まれた。
わかったような、わからないような説明である。古典派の時代は一応18世紀後半から19世紀初頭、ロマン派の時代は19世紀いっぱいから20世紀初頭、くらいに考えてよいが、古典派の時代にも人間の感情を切々と歌い上げた作品はいくらでもあるし、ロマン派の時代にも絶対音楽はたくさん書かれているのである。それに、ロマン派における様式感というものは、ほとんどすべて、古典派の時代におけるそれの上に構築されている。
外見上、そんなに差があるようには見えない。
そのため、学者によっては、これらを「古典・ロマン時代」とひとくくりにして扱い、バロック時代とかルネサンス時代とかに対比させている。
だが、私の意見では、やはり古典派とロマン派の間には、決定的な差がある。
音楽だけ見ていたのでは、その差はわかりずらい。
古典派の時代、すなわち18世紀後半。
これはまさに、フランス革命の時代なのである。この時代に生きた音楽家は、多かれ少なかれ、フランス革命の、少なくともその精神の影響を受けている。
フランス革命の精神とはなんだったのだろう。
個々の革命家たちには、いろんな思惑があっただろうが、とにかくそのバックボーンとなったのは、
──普遍への確信
といったものではなかったかと思う。
この世の中には普遍的真理というものがあって、それに則ることによって誰もが幸せになれるのだという確信。それがフランス革命の理念だった。
フランスが自らの王政を打倒したのち、すぐさま他の国に対して革命の輸出をもくろみ始めたのは、その確信があってこそのことなのである。
フランス革命は普遍的真理を体現したものなのだから、これに反対する者は、ひっきょう普遍的真理への敵であり、打倒されなければならない。彼らはそう信じていたであろう。今世紀の社会主義革命の論理となんと相同的であることか。
フランス革命に与すると与しないとを問わず、
──普遍的真理というものが存在する。
という気分は、ヨーロッパ中にみなぎっていたはずである。
古典派の音楽とは、そういう気分を背景にして確立されたものなのである。
形式が重んじられた、と教科書には書かれている。形式とは、
──それに則りさえすれば、誰でも普遍的なものが作れる
ものでなければならない。実際、ソナタ形式という形式をマスターし、それに則って作曲すれば、それなりの音楽はできるのであって、今でも音大作曲科の受験生たちが必死で勉強しているはずである。
この時代の作曲家たちは、意識するとせざるとを問わず、この大いなる普遍に向かって叫ぶことができた。彼らの作品は全世界に通用するはずであった。
このスタンスが確乎としてあったればこそ、この時代の音楽は、「古典(クラシック)=ならうべきもの」という栄誉ある呼称を、後世から捧げられることになったのだった。
この普遍的真理の伝道者が、ナポレオンに他ならない。
ナポレオンは、フランス革命の理念そのものであった。
やはり普遍的真理への賛美者であった(つまり骨の髄から古典派であった)ベートーヴェンは、当初ナポレオンに対し、大いに共感を覚えていた。
彼が畢生の大作である第3交響曲を、ナポレオンに献呈するつもりだったことはよく知られている。
だが、ナポレオンはベートーヴェンの期待を裏切って、皇帝の座についた。
よく誤解されているが、ナポレオンは「フランス皇帝」になったのではない。フランスは断固として共和国であり、帝国ではないのだから、皇帝がいるはずがない。ナポレオン自身、フランス人に向かって呼びかける時は、たかだかと
「共和国市民よ!」
と叫んでいる。
ではナポレオンは一体どこの皇帝だったのだろうか。
実は彼は、「世界皇帝」になったのである。
全世界を統治する最高支配者。それがナポレオンの称号であった。
自分は普遍的真理の体現者であり伝道者である。従って、自分は普遍的真理と共に全世界に君臨しなくてはならない。ナポレオンの論理は、そういうものだった。
現在のスウェーデン国王は、ナポレオン配下の将軍のひとりが、ナポレオンに任命されて国王に就任したのがはじまりである。ナポレオンは世界皇帝であるがゆえに、支配下の各国の国王を任命できたのだ。
しかし、このナポレオンの振る舞いは、フランス人にとっては溜飲の下がるものだったろうが、彼に支配されることになる他の国々にとっては、笑止千万としか言いようのないものであった。
各地に、ナポレオン及びフランスに反抗する勢力が、澎湃として湧き上がってきた。
ナポレオンが「普遍的真理」によって武装している以上、それに反抗する勢力もなんらかの理論武装が必要となる。
それが、ナショナリズムであった。
それまでのヨーロッパに、ナショナリズムなどはなかったのであって、国境ひとつにしても、王家の結婚だの相続だのでころころと変化するものだった。誰もがそれを当然と思っていた。
だが、ナポレオンの強引な「普遍的真理」の伝道は、現象としては周囲の国々への大侵略となり果て、大汗かきながら各地にナショナリズムを植えつけて廻るという、皮肉ともなんとも言いようのない結果になった。
ロマン派というのは、基本的にはこのナショナリズムの上に形成された思潮なのである。
各地の伝統や風俗を見直し、そこから素材を求めることによって自らの表現をおこなってゆく。さらにはそういう地域性さえも離れ、自分自身の感情や考え方にこだわる。
普遍とは正反対のベクトルを持つ動きなのである。
シューマンは、もっともロマン的な作曲家と言われているが、彼の「謝肉祭」などを見ると、彼自身の友人やガールフレンドの名前を冠した小曲が連ねられている。その中でたまたま、ショパンやパガニーニ、それにのちに彼の妻になったクララ・ヴィークなどは名が知られているからいいようなものの、
──誰、それ。
と言いたくなるような名前も少なくない。つまりシューマンは自分の個人的な生活をそのまま作品に投影したのであって、ベートーヴェンならそんなことは決してやらなかっただろう。この、臆面もない内輪受けの作品が、結構世の中に受け容れられる、そのこと自体が、すでに世界が普遍へのベクトルを失っていることを如実に示している。
ベートーヴェンは、ナポレオンが帝位についたことを知ると、すでに献辞まで書き添えてあった第3交響曲の表紙を破りとり、床にたたきつけて、こう叫んだという。
「あの男も結局、ただの人間に過ぎなかったのだ。彼もまたおのれの野心を満たすため、あらゆる人々の権利をその足許に踏みにじるだろう。しかも、今までに存在した誰よりも暴君となるだろう」
ベートーヴェンの胸中にはこの時、普遍的真理というものへの疑いが兆したのではないか。
このあと、ベートーヴェンは次第に、自らの作品にドイツ語の発想標語を書きつけるようになってゆく。
言うまでもなく、音楽用語のほとんどはイタリア語である。もし音楽が普遍であるなら、発想標語は作曲者の国籍にかかわらず、イタリア語で充分なはずである。だが、普遍というものが幻想であるならば……
それならば、発想標語は自国語で書くべきではないのか。その方が間違いがない。
ベートーヴェンの生涯の中期後半、作品番号で言えば60番台から90番台あたりにかけては、彼の動揺がはっきりと見てとれる。第5交響曲(運命=作品67)と第6交響曲(田園=作品68)が同時に書かれていることに注目すべきだろう。どちらも名作ではあるが、明らかに、第5番には普遍への、第6番にはナショナリズムへのベクトルが感じられる。彼の生涯の友とも呼べるピアノソナタすら、この時期は4曲(第24番「テレーゼ」、第25番「カッコウ」、第26番「告別」、第27番)しか書かれておらず、しかもそのどれもが、著しく精彩を欠いた小品風なものにとどまっている。ベートーヴェンにはこの時期、大いに迷いがあったとおぼしい。
ヴェーバーやシューベルトなどの新世代の作曲家たちの活躍も気になっていただろう。ヴェーバーは「魔弾の射手」においてドイツの伝承を扱い、ドイツロマン主義の尖兵となった。シューベルトは母国語によって自然な感情の発露を歌い上げていた。どちらも、普遍には背を向け、自国ないし自己に眼を注いでいる。
自分のやってきたことは間違っていたのではないか。ベートーヴェンの心が揺らぐ。
ベートーヴェンの後期がロマン派であるという主張は、この意味においてなされるべきなのである。
1813年に、第7交響曲と第8交響曲をほぼ同時に発表したのち、ベートーヴェンはぱったりと交響曲を書かなくなる。第1交響曲を発表したのは1800年であったから、彼は13年で8曲の交響曲を矢継ぎ早に書いてきたことになるが、次の交響曲を発表したのは、11年後の1824年だった。8曲書くのに要した時間と、8番から9番までに要した時間が、そんなに違わないのである。
この空白の時間は、ベートーヴェンの迷いがそれだけ大きかったことを示しているのではあるまいか。
しかし、交響曲こそ書かれなかったが、この時期には数々の傑作も生まれている。今なおピアノ音楽の最高峰と言える後期5大ソナタと「ディアベリ変奏曲」。それに荘厳ミサ曲が挙げられよう。これらの作品は、ベートーヴェンが再び普遍への賛歌に戻ってくるための里程標であったように、私には思われる。5大ソナタのうちでも特に巨大な風貌を持つ第29番「ハンマークラヴィーア」には、すでに「第九」への確かな鼓動が感じられてならない。
5大ソナタと変奏曲で、ぐらついていた普遍への確信を取り戻し、さらに荘厳ミサで、声楽とオーケストラの合体した響きを追究する。かくて、「第九」への道は敷かれた。
──やはり、音楽はこうあるべきなのだ。普遍へ向かって大声で叫ぶべきだったのだ。
「第九」は、ベートーヴェンのそうした確信の集大成であったのである。
歌詞こそドイツ語だが、発想標語はことごとくイタリア語に戻っている。シラーによる歌詞そのものが、きわめて大いなる普遍への賛歌でもある。
第4楽章の冒頭で、それまでの3楽章のモティーフが次々と回想されては打ち消されてゆくが、それはすべての迷いを退けたベートーヴェン自身の姿なのだろう。そしてバリトン独唱の決然たるプロローグ……
「おお、友よ、このような調べではない!
より美しく、歓喜に満ちた調べに、共に声を合わせようではないか」
ナポレオンの誤った普遍の伝道とも、偏狭なナショナリズムともはっきりと訣別し、自らの信ずる真理を高らかに宣言するベートーヴェンの獅子吼が聞こえるようではないか。
ベートーヴェンは、その生涯の後半、確かにぎりぎりまでロマン派に傾きかけた。
だが、「第九」によって、やはり普遍的真理を確信した古典派の巨匠であることを証明したのである。
はたして、ベートーヴェンは正しかったのか?
音楽に普遍はありやなしや?
そのひとつの答えが、時間的にも空間的にも遠く離れた極東の島国で、普段はクラシック音楽などとは風馬牛の「普通の」ひとたちが、「第九」を歌うために押し寄せてくる現象の中にあるように思える。
難しいことを言わなくても、これこそ「真のクラシック音楽の理解」そのものではないだろうか。
(1998.12.7.)
|