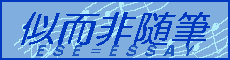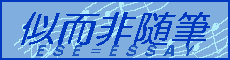ドビュッシー vs.サティ vs.ラヴェル
クロード・アシル・ドビュッシー(1862-1918)、エリック・サティ(1866-1925)、そしてモーリス・ラヴェル(1875-1937)の3人は、いずれもフランス近代音楽の旗手としてよく比較される。
3人とも偉大な仕事を成し遂げたことは間違いないし、天才の名に価するのも確かだが、決して単独で出現した才能ではない。19世紀初頭からの、フランスにおける緻密な音楽教育システムの成果と言うべきではないかと思う。彼らに先行するグノー(1819-1880)、フランク(1822-1890)、サンサーンス(1835-1921)、ビゼー(1838-1875)、マスネ(1842-1912)フォーレ(1845-1924)といった錚々たる顔ぶれが充分に地ならしをした上に花開いた大輪の花なのである。
確かに、この中でアカデミックな修業を順調にし遂げたのは、比較的世渡りもうまかったドビュッシーだけで、ラヴェルはフォーレの薫陶を受けながら結局ローマ大賞(パリ音楽院から与えられる作曲賞で、受賞者は1年間ローマに留学できる)を獲得できず、サティははなからアカデミックな音楽教育など受けずに自己流で作曲をしていたのだが、それにしてもやはり、3人の存在はフランスの教育熱心な風土が産み出したものだと考えてよいのではないだろうか。
なお、ラヴェルがローマ大賞を落とした件に関しては、当時かなり物議を醸し、いわゆる「ラヴェル事件」として、パリ音楽院の院長だったデュボワが辞任する騒ぎにまでなっている。すでに「水の戯れ」など多くの名曲を送り出しているラヴェルを落とすとは何事だと抗議した人々が沢山居たのである。
さて、3人の作品を比較すると、それぞれ独特な色彩感を持ちつつ、どれを聴いてもいかにもなフランス音楽であるところが共通している。ひとことで表現するなら、ドビュッシーの音楽を特徴づけるのは陰翳の柔らかさ、サティは荒削りなユーモア、ラヴェルは息苦しいほどの緻密さといったところだろうか。そういう意味では同じ才能でも、ドビュッシーを天才型、サティを奇才型、ラヴェルを秀才型と呼んでも差し支えないようではあるが、ラヴェルの「ボレロ」を見ると、これは決して狙ってできる作品ではないようでもあり、そういう安易な分類を拒否する部分も少なくない。
3人はそれぞれに面識があった。ドビュッシーとサティのエピソードはよく知られている。
サティがあまりにも妙な曲ばかり書いているので、4つ先輩に当たるドビュッシーが忠告したというのだ。
「君は、もっと形式のしっかりした曲を書くべきだ」
サティはかしこまって聞いていたが、そのまま素直に従う男ではない。この忠告に応えて作曲したのが、ピアノ連弾のための「梨の形式による3つの小品」(MIDIは第1曲)である。ドビュッシーはもちろんソナタ形式とかロンド形式とかの意味で言ったのだが、サティは裏をかいて「梨の形式」などというわけのわからないものを作ったわけだ。ちなみにフランス語の梨(poire)には「のろま、とんま」という意味がある。しかもこの曲は「3つの小品」と称しつつ、3曲の主要楽章の他「はじまり」「はじまりの続き」「おまけ」「おまけの続き」というのがあって全部で7曲よりなっているという人を食った作品なのだ。
もっともこの話は、本当にはなかったという説もある。ドビュッシー自身が次第に既成の形式を超越してゆくのだから、あまり信憑性のある伝説ではない。
そのドビュッシーは、13歳年下であるラヴェルを、ライバルとしてかなり意識していたとも言われる。彼のピアノ組曲「映像・第1集」の冒頭に置かれた「水の反映」は、上記の「水の戯れ」に対抗して書かれたと伝えられるのだが、私はどうかなと思う。水というテーマを用いることに、別に影響も対抗もないのではないだろうか。
ただ、ラヴェルがドビュッシーを訪ねて、自作の「クープランの墓」を弾いたというのは本当らしい。実はラヴェルの自演の「クープランの墓」のレコードが実在しているのだが、最後のトッカータなどはおそろしくテンポが遅くて、後半部分のめくるめくようなクライマックスは台無しになっているそうだ。書いてはみたものの自分では指定のテンポで弾けなかったらしい。ところが、ドビュッシーはラヴェルのそのたどたどしい演奏を聴いて、大いに褒め称えたという。
この3人はいずれも「印象主義」と言われるのだが、はたして印象主義とは何かとなると定義しずらい。開き直って、
――この3人の作品のような傾向の音楽だ。
と言ってしまった方が話が早いほどであるが、そうは言っても三者三様で、なかなか共通のものを抽出するのは難しい。
ただ、3人とも、当時ヨーロッパに上陸したジャズに大いに影響されたことは間違いない。ジャズ好みは彼らの後輩に当たるオネゲル(1892-1955)、ミヨー(1892-1974)、プーランク(1899-1963)などにも受け継がれ、フランスの作曲家のお家芸のようになった。
また、音楽以外の交際からの影響が大きいことも見逃せない。
ドビュッシーは詩人のマラルメや画家のモネなどと親しく、この両者から非常に多くの影響を受けている。特にモネの点描画法はドビュッシーの書法にきわめて深い関係がある。
サティは作家のジャン・コクトーや画家のピカソなどと親しく、一緒にミュージカルのようなものも作っている。「パラード」などが有名だが、コクトーの斜に構えたような創作態度やピカソの抽象絵画には大きく影響されるものがあっただろう。
ラヴェルの交友にはそれほどのビッグネームは見られないようだが、エドガー・アラン・ポーやマラルメの詩を愛読したことは伝えられている。「夜のガスパール」などは明らかにポーの詩に影響されたものだ。
いずれにしろ、フランス音楽のみならず、20世紀初頭の音楽風景において、彼らを除外することは絶対にできない。それぞれに偉大な作曲家たちであった。
スクリャビン vs.ラフマニノフ
同じ頃、ロシアでもふたりの音楽家がしのぎを削っていた。アレクサンドル・スクリャビン(1872-1915)とセルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)である。このふたりは生まれがわずか1年差でもあり、全く同時期にモスクワ音楽院で学んだこともあり、フランスの3人よりもはるかにお互いを意識せざるを得なかっただろう。
後世の好事家にとってありがたいことに、このふたりは、実際に「勝負」している。勝負と言っても、昔の演奏合戦のようなものではなく、1892年のモスクワ音楽院の卒業演奏でのことである。この時、ラフマニノフが1等、スクリャビンが2等だった。言うまでもなくこの種のコンクールの1等2等は、審査員の好みにもよるので、それほどの技量の差があったわけではないだろう。甲乙つけがたい演奏であったに違いない。
このエピソードでわかる通り、ふたりとも卓越したピアニストだった。そのことは両者のピアノの作品を見てもすぐにわかる。どちらもおそろしくハイレベルのテクニックを要するが、一旦憶えてしまうと、これほど指を楽しませることのできるピアノ曲もそうそうはない。ラフマニノフは非常に手が大きく、12度(ドからオクターブ上のソまで)を楽につかむことができたと言う。また、スクリャビンは在学中に右手を痛めたことがあって、その間左手の猛特訓をしたため、彼の作品では左手が縦横に活躍する。
作曲家として比較するとどうだろうか。
初期作品は、いわゆる後期ロマン派の重厚華麗な雰囲気にどっぷり漬かっており、ある意味ではかなり似たところもあったふたりだが、やがて対照的な作風になってゆく。
よく、スクリャビンは未来を向き、ラフマニノフは過去を向いていたと片付けられることがある。スクリャビンはある時期から、従来の和声組織を捨て、神秘和音なるものを用い始める。その方向は確かに複調化、無調化のベクトルを含んでおり、その意味では現代音楽につながるものがある。一方、ラフマニノフは最後まで機能調性を捨てず、チャイコフスキーの継承者としての存在であり続けた。
だが、無調的だから未来向き、調性的だから過去向きという簡単な二分法が通用したのは70年代頃までであって、現在は20世紀の音楽風景そのものを見直そうという時期に入っている。このふたりの存在意義も、また新たな視点から顧みてみる必要があるのではないだろうか。
私が弾いたり聴いたりした限りにおいては、スクリャビンの作品は基本的に、非常に楽観的な曲想を持っている。木漏れ日がきらきらと降り注いでいるような印象を覚えるのである。晩年は神学に凝り、曲の内容も神学的になっているのだが、考えてみれば神学というのは大いなる楽観に他ならない。最終的には神様がなんとかしてくれるという確信があってこそのものだ。
これに対し、ラフマニノフはどうにも悲観的である。代表作のピアノ協奏曲第2番などを聴いただけでもわかるが、やりきれないもどかしさのようなものが、彼の作品には常にたぎっているように思える。1917年のロシア革命を予想しているかのようでさえある。
ちなみにスクリャビンは革命を待たずして48歳の若さで他界した。ラフマニノフは革命後スウェーデンを経てアメリカに渡ったが、亡命後の作品にはあまり見るべきものがない。いずれにしても、彼らがそういった時期に生きていたということは、念頭に置いておく必要がある。
スクリャビンの神秘和音は、特に後継者もなく、単発的な実験に終わった。よりラディカルなシェーンベルクたちの方法(十二音技法)が広まってしまったのだ。その意味で言えば、必ずしも未来を向いていたとは言い切れない。一方でラフマニノフの不安と焦燥に満ちたパトスは、紛れもなく今世紀のものだったのではないだろうか。そして実際、玄人筋の白眼視にもかかわらず、ラフマニノフの作品はスクリャビンよりもはるかに、今世紀の一般聴衆に受け容れられてきた。
個人的なことを言えば、私はスクリャビンが好きで、「好きな作曲家は」と問われればためらわずにバッハとスクリャビンを挙げる。スクリャビンが未来向きだったとすれば気分はいいのだが、冷静に考えればかくのごとしである。要するに、ふたりとも自分の感性と信念に従って作曲したのであって、その情熱に決して差はない。
4回にわたって「ライバル音楽史」を書いてきた。もちろんこの他にも、比較して面白い人たちは沢山いる。演奏家同士の対決にも触れるべきだったかもしれない。が、近い時代になるとまだそれぞれの評価が定まっていないし、特に存命の人であればやや失礼な気もするので、とりあえずここまでにする。また興が向いたら、誰かを俎上に乗せて比較検討してみようと思う。
(1998.6.15.)
|