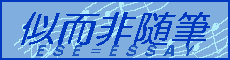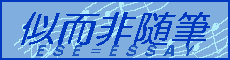|
「才能は群生する」という説がある。
歴史を眺めていると、さまざまな偉大な人物が居るものだが、そういう人々が妙にたくさん輩出した時期と、それほどでもない時期があるのに気づく。しかも、輩出した場合、そんなに広域ではなく、わりに狭い地域の中で、よくこれだけの才能が集まったものだと驚くことが多い。
全く孤立した、いわば超天才というべき輝きを放っている人もいないではないが、天才というもの、やはり他の才能に出逢うことによって、より切磋琢磨されて生まれてくるのが普通なのかもしれない。「天才」の定義にいま深入りをするつもりはないが、私は天才はあくまで社会との関わりの中で出現するものだと思っている。その意味では「知られざる天才」というのは存在しないのだ。ある人間の為したことが、ある時期の社会の要請や好みと交わって光を放った時、人は彼を天才と呼ぶのではなかろうか。
近い時期に生き、近い場所に住んで、互いにまさるとも劣らぬ輝きを放っている人間が複数いた場合、われわれはついその人々を比較したくなる。
いや、比較できるのは、天才ならざるわれわれの、大いなる楽しみというべきだろう。本人たちがどう思っていたかなどには関係なく、われわれは彼らをひと組の「ライバル」として扱い、それぞれの能力を比較してはうち興じるのである。
音楽史上にも、火花散るライバル、と思われている人々が何組も存在する。
これから数回にわたって、そのいくつかを扱い、比較する楽しみを味わってみよう。
レオナンvs.ペロタン
西洋音楽史で、最初の「作曲家」と呼べるのは、12世紀後半にパリで活躍していたと伝えられるレオナンである。その生涯はおろか生没年さえわかっていないが、当時の総合大学と呼ぶべきノートルダム寺院に集った音楽家(音楽はヨーロッパでは最初から大学の正課だった)たちの頂点に位置していたことは間違いない。
だが、このレオナンにも、すぐさまライバルが出現する。レオナンの後輩とも弟子とも伝えられるが、やはりその生涯はなにひとつ不明な、ペロタンである。ペロタンはレオナンを凌駕する才能の持ち主だったといわれるが、それが作曲に関してなのか、演奏に関してなのかもわかっていない。さすがに800年前の人たちだけあって曖昧模糊としているが、音楽史の黎明期からこういうライバル関係が発生していたというのは面白いではないか。
これはやはり、ノートルダム寺院という一大学府があり、多くの才能が集まってきたことによって磨かれたものに違いない。
J.S.バッハvs.ヘンデル
一気に時代は飛ぶ。ルネサンス期にも多くのすぐれた作曲家はいるが、取り立ててライバル関係と見なして比較するほどのグループは見当たらない。パレストリーナ、ラッスス、ビクトリアなどを較べてもよいのだが、彼らは別々の国で全く別個に活躍しており、「ライバル」と呼ぶのは無理があるようだ。
やはり、われわれの興味を惹くのは、「音楽の父」J.S.バッハと、「音楽の母」ヘンデルの「対決」である。ふたりとも1685年にドイツで生まれ、膨大な作品と卓越した演奏技術を併せ持った巨匠である。
残念ながら、このふたりは顔を合わせてはいない。手紙をやりとりしたことはあるようだが、バッハがもっぱらドイツ国内で活動していたのに対し、ヘンデルはイタリアに英国にと飛びまわっていたので、会う機会はなかったのである。
生前の知名度は、ヘンデルの方がはるかに高かった。バッハはいささか偏屈でアクの強いところがあって、人とよく衝突していたようなので、対人的な人気もなかったのかもしれない。残っている肖像画を見ても、バッハの因業オヤジっぽい風貌に較べ、ヘンデルは上品な紳士という感じがする。が、ふたりの知名度の差の大きな原因は、やはり当時文化的後進地域と見なされていたドイツを離れたか離れなかったかにあるのではないかと思う。
現代の評価は明らかに逆転している。バッハはそのほとんどの作品が、今でも演奏され続けているが、ヘンデルの作品でしばしば演奏されるのは、「メサイア」及びいくつかの小曲に過ぎない。ひとつにはヘンデルが力を入れたバロック・オペラが、あまりはやらなくなっているせいだろう。バッハはオペラをついに一曲も書かなかった。今後、バロック・オペラのブームでも到来すれば、ヘンデルが再評価される時代も来るかもしれないが、やはり史的意義としてはバッハの存在の方が大きかったと言えるのではなかろうか。
ヘンデルvs.D.スカルラッティ
ところで、1685年にはもうひとりの大作曲家が生まれている。バロック・オペラの大家アレッサンドロを父に持つ、ドメニコ・スカルラッティである。彼は生涯ハープシコードの作品のみを作り続けたという点で、「バロックのショパン」と呼んでもよい存在だ。実際その作品にも、ショパンと共通する、洒脱さ、華麗さ、品の良さ、よい意味での通俗性、などがあふれている。試みに有名なソナタL.23の冒頭部分を掲載しておく。
ただ、バッハやヘンデルのような異様にエネルギッシュな印象はないため、このふたりと並べると少々影が薄い。
彼はもっぱらイタリアで活動していたので、バッハとの接点はなかったが、コスモポリタンのヘンデルとは顔を合わせている。しかも、実際に「対決」を行っているのである。
というのは、18世紀まで、音楽の対抗戦というものが、貴族の館などで好んで行われていたのである。ヴァーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」などを考えていただきたい。あれは歌合戦だが、歌に限らず、いろんな楽器の演奏をお抱えの音楽家に競い合わせ、優劣を判定するという「競技」が、上流階級の楽しみとされていた。今の感覚だと、音楽家には失礼な話だが、当時の音楽家は別に「芸術家」などではなく、一種の「職人」と見なされていたことを考えなければならない。
さて、時は1709年、ローマの枢機卿オットボーニの館で、ヘンデルとスカルラッティは対決した。共に24歳、新進気鋭の若手同士である。
勝負は、ハープシコードの即興演奏で行われた。
かたや若くしてすでにヨーロッパ中にその名を知られた天才、かたやイタリアの誇る大音楽家の家系に生まれたサラブレッド……さすがに両雄相譲らず、先攻のスカルラッティが華麗な超絶技巧で攻めれば、ヘンデルは重厚な深みのある音で受け、聴いている客たちもやんやの大喝采、とても甲乙つけがたかった。
結局、このハープシコード勝負では引き分けとなってしまい、翌日、異例の第2回戦が開催された。
今度は、オルガンの即興演奏勝負である。
ヘンデルが先攻となった。彼は椅子に座り、しばらくのコンセントレイションののち、おもむろに重々しい和音を叩き始めた。それはやがて変容され、技巧的なパッセージを伴って駆け上がり、華やかなトッカータとなった。
一段落ついたかと見る間に、印象的な主題が出現し、それをもとにして燦然たる大フーガが展開される。聴く者は言葉を失い、涙する者さえ見られたという。
演奏を終わって、ヘンデルは一礼し、後攻のスカルラッティに、促すような仕草をした。
スカルラッティはしばらく無言で立ちつくしたのち、ヘンデルに握手を求め、にっこりと笑って、
「私の負けです」
と言った。
勝者であるヘンデルに喝采が寄せられたのは当然だが、投了したスカルラッティの潔い態度にも賞賛が寄せられ、ふたりの評判はますます高まったという。また、こののちヘンデルとスカルラッティは固い友情で結ばれ、生涯文通を続けたそうである。
この種の「勝負」は19世紀に入ると行われなくなったので、直接の「ライバル対決」として興味深いのは、残念ながら音楽史を通してこの一例のみである。古典派時代になって、モーツァルトとクレメンティが勝負した話もあるが、これは判定を下すべき貴族が熱烈なモーツァルトファンで、公正な判定を下さなかったと言われているので、ここに取り上げるのには適当でない。
次回は、古典派からロマン派にかけて扱おうと思う。
(1998.3.16..)
|