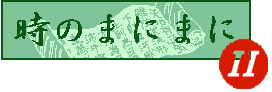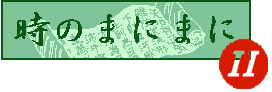|
前漢は王莽(おうもう)の簒奪により亡ぼされ、新という王朝ができますが、失政が続いたためわずかな期間で打倒されてしまいます。群雄割拠の末、最終的に勝利者となったのは漢の宗族のひとりであった劉秀で、彼が後漢の光武帝となります。
宗族というのは、皇族のうち民間に下った者を指します。清王朝のときに、王朝創始から200年ほど経った時点で皇族が2万人以上に達し、清は彼らに洩れなく生活費を支給していたため、それだけで財政難の原因になっていたと言います。漢はそれほど身内に寛容ではなく、皇族をどんどん民間に放出しました。彼らは自力で食ってゆかなければならなかったわけです。前漢末期にはやはりすでに数万人くらい居たと思われますので、そのひとりである劉秀は、確かに漢皇室の血は引いていますが、事実上は一庶民みたいなものだったでしょう。さらに200年近く後の後漢末に、やはり漢の宗族であった(と言われている)劉備が、ムシロ売りをして日銭を稼いでいたことが思い出されます。
そんなわけで、後漢は前漢と同じく漢の国号を名乗ってはいますが、それは皇帝の姓が同じだからというだけの話で、実際には別の王朝と考えて良いと思います。
さてこの後漢は、前に書いたとおり、宦官の害が甚だしかった三朝のひとつとされています。
そしてその理由もはっきりしています。後漢は早死にの皇帝が多く、それゆえ後継者がほとんど幼少のうちに即位し、つまり幼君であるケースが多かったためです。
初代の光武帝は30歳で皇帝になり62歳まで生きましたので、まあ当時としては短命とは言えません。初代皇帝というのは、早死にすると政権が安定しませんので、光武帝がまあまあの寿命をまっとうしたのは幸運だったと言えるでしょう。
光武帝以後、後漢には12人の皇帝が居ますが、その中で50代まで生きたのは最後の献帝だけです。献帝と言えば、三国志では群雄に翻弄された揚句に曹丕によって国を奪われた悲運の皇帝として多くの人の同情を買っていますが、実際にはなかなかしたたかな人物であったようで、皇帝の重責を投げ出してよほど気楽になったのか、簒奪者の曹丕よりずっと長生きしました。しかも退位後もほとんど皇帝待遇を許されたというのですから、ある意味では勝ち組だったようでもあります。
光武帝と献帝を除いて、40代まで生きたのは2代目の明帝ただひとりです。30代で死んだのが3代章帝、6代安帝、10代桓帝、11代霊帝の4人、20代で死んだのは4代和帝と7代順帝、あとの4人は20歳になる前に歿しています。5代殤帝、8代冲帝のごときは、ほとんど赤ん坊のうちに即位して死去しており、自分が皇帝だという自覚すら無かったことでしょう。
こんなに若死にばかりしているので、子供が居たとしてもまだ幼いのは当然で、子供を作れなかった皇帝も何人か居ます。その場合は傍系の皇族から即位することになりますが、成人した皇族では周囲が何かとやりづらく、やっぱり子供を連れてくるということになりがちだったのでした。
寿命もさることながら、即位した年齢を見るとさらに驚きます。2代明帝が29歳で即位しているのを除くと、3代目以降はすべて20歳以下、うち5人は10歳以下です。
まるで呪いでもかかっているかのような短命ぶりですが、どうも妙な薬を服んでいたせいであるようです。五石散、というのは少し後の魏晋時代に大流行した薬ですが、後漢期にも似たようなものはあったに違いありません。
当時の考えかたとしては、動物や植物に由来する薬は、もともと死ぬものから作られているゆえにあまり効果が無いと思われていました。死なないものと言えば鉱物です。鉱物から作られた薬こそ、不老長寿に効果抜群の妙薬と考えられました。
そんなわけで、砒素やら鉛やら水銀やらがてんこ盛りに含まれた薬物を、当時の人々は争うようにせっせと服用しました。もちろん至尊の存在たる皇帝陛下には、特にえりすぐって精製されたものが献上されたはずです。こんな薬を毎日のように服み続けていれば、早死にするのも当然でした。
さて、幼帝が続くとなぜ宦官がはびこるのかと言うと、後宮、つまり皇帝の私生活の場には女性と宦官しか居ないからです。皇帝のおおやけの仕事の場は朝廷で、こちらには宰相以下男性ばかりが並んでいるわけですが、幼少な皇帝はあまり朝廷には顔を出しません。
皇帝が幼い場合、宮廷の意思決定はその母に委ねられます。つまり皇太后です。皇太后は必ずしも皇帝の生母とは限りませんが、後漢では皇太子が決まった時点でその生母が皇后に立てられるということも多かったようです。
皇太后というと年配の女性をイメージしますが、20代や30代で歿した先帝の皇后だった人ですから、やはりだいたい20代、中にはハイティーンの皇太后も居ました。
章帝の皇后だった竇(とう)氏のように、なかなかやり手だった人も居たものの、やはり一般的に若い女性では政治のことはわからないと言えましょう。現代のように大学で政治学を学べるわけでもありません。
そこで年若き皇太后が頼るのは、実家の父や兄ということになります。いわゆる外戚です。この外戚がわきまえのある連中であれば問題はないのですが、往々にして自分の一族の者を要職に就けたりして、専横を振るうようになります。困ったことに、出世した者が家族や親戚の便宜を図るのは、近代国家では汚職と見なされますが、中国の伝統的価値観においては、まごうことなき「正義」なのでした。彼らは外戚という自分の地位を利用して一族を引き立てることに、なんのうしろめたさも感じていません。当然の権利だと思うばかりでした。
何しろおいしい地位ですので、政柄を握った外戚は、幼少だった皇帝が成長しても、なかなか大権を返そうとしません。そうすると当然皇帝は面白くありません。自分は一天万乗の君と教えられているのに、何かやろうとしても滅多に思いどおりになることが無く、母方の祖父さんや伯父貴がやたらと口を出してくるのはいったいどうしたことだろうかと、不思議に思います。
そういう皇帝が相談する相手といえば、どうしても幼い頃から身のまわりに居て世話を焼いてくれている「宦官」ということになってしまうのでした。
宦官は自分たちの仕える皇帝に力があったほうが、役得も大きくなります。前に書いたとおり、皇帝に嘆願の儀がある者は、皇帝の信頼の篤い宦官に口を利いて貰おうとして、莫大な礼物を贈ったりするのです。外戚に牛耳られている皇帝では、その外戚に頼んだほうが早いので、皇帝周辺にも役得は少なくなります。
もちろんそんな欲得ずくばかりではなく、純粋に仕えている皇帝に同情した者も多かったでしょう。宦官たちは皇帝に本来の権力を取り戻すべく、外戚の力を削ごうとします。
後漢一代は、こうした外戚と宦官のせめぎ合いの繰り返しでした。その他に国の中核を占める知識人たる士大夫階級の人々が居て、時に外戚と対立したり同調したりして、三つ巴の政争になることが珍しくなかったのです。
その中で宦官を中心とする勢力は、「濁流」などと言われたりして、どうしてもダーティなイメージがつきまといますけれども、ダーティさなら外戚や士大夫も似たり寄ったりで、宦官勢力だけがたちが悪かったわけではありません。
最初に外戚と宦官が衝突したのは和帝の時で、竇太后とその一族から権力を取り戻そうとした和帝が、宦官鄭衆を頼んだことにはじまります。
鄭衆はまじめな宦官で、心底和帝のためを想っていたようです。彼は竇氏一族の総帥である大将軍竇憲(とうけん)の実権を奪い、自殺させることに成功し、見事に和帝に権力を取り戻しました。政治的にも有能であり、しかも自制の利いた人物で、その後の和帝からの絶大な信頼にもおごることなく職務をまっとうしました。
鄭衆がこのように優秀な人物であったのが、かえって良くなかったかもしれません。その後の明らかに質の落ちた宦官たちを、歴代皇帝が変わらず頼みにしていたのは、鄭衆の余徳というものだったでしょう。
和帝の時代には、もうひとり大物の宦官が居ました。蔡倫です。
長らく「紙の発明者」とされていましたが、類似のものがもっと早い時期からあったことが判明して、現在では「紙の改良者」という位置づけになっています。ただその「類似のもの」は鏡を包んでいた包装紙で、文字などが書かれた形跡はありません。現代と基本的に同じ製紙法を確立したのが蔡倫だったと考えて良いでしょう。
彼の開発した紙は特に「蔡侯紙」と呼ばれました。その呼ばれかた自体、類似のものがそれ以前からあったことを示しているようですが、いずれにしろクオリティが段違いであり、蔡侯紙の名はまさにブランドでした。
「蔡」は彼の姓ですが、「侯」というのは彼が竜亭侯という爵位を貰っていたからつけられた敬称です。宦官なのに諸侯に取り立てられたのは、蔡倫が最初ではないにせよごく初期のひとりでした。
蔡倫は残念なことに、安帝期の政争に巻き込まれて自殺に追い込まれてしまいます。しかし、彼は宦官としてではなく、諸侯として自裁したのでした。不朽の業績と誇り高い死にざまは、後世の硬骨の宦官たちの憧れ、模範になったと思われます。
安帝も、和帝の皇后だった鄧(とう)氏の一族の専横に反撥して、宦官李閏(りじゅん)を頼んで打倒を図ります。鄧氏はわきまえのあるまじめな女性であり、その一族も決して「専横」というほどの傍若無人な権勢を振るっては居なかったようですが、安帝にとっては息苦しかったのでしょう。しかし李閏と共に頼みにした自分の皇后閻(えん)氏の一族は鄧氏よりずっと質が悪く、李閏も鄭衆ほどのすぐれものではなかったようです。
その閻氏を打倒しようとしたのが順帝です。順帝も宦官を頼りにし、孫程(そんてい)らの尽力により打倒に成功します。
順帝の皇后は梁(りょう)氏で、この女性はなかなかよくできた人だったようですが、その兄の梁冀(りょうき)が最悪の外戚でした。無能なくせに権勢欲だけは強く、しかも猜疑心旺盛で、気に食わない者をすぐ陥れて処刑するような人物でした。質帝などはこの男を
──跋扈(ばっこ)将軍。
と呼んだだけで毒殺されています。わずか8歳で、深い意味は無かったと思われるのですが、梁冀は子供に悪口を言われただけでも許せないという狭量な男だったのでした。
質帝を毒殺したあとに梁冀が擁立したのが桓帝でしたが、14歳で即位した桓帝も、数年経つと当然のように梁冀を憎み、宦官単超(ぜんちょう)と図ってこれを族滅しました。何度同じことを繰り返せば良いのかと言いたくなります。
しかも桓帝は、ここで取り返しのつかない誤りを犯してしまいます。宦官たちの働きに感激するあまり、爵位を大盤振る舞いして、一挙に「宦官諸侯」を増やしたばかりか、宦官に養子をとることを認めてしまったのでした。
宦官は男性機能を失っていますので、子孫は残せません。だから爵位も財産も一代限りでした。ところが養子をとれることになったので、地位や財産を受け継がせることが可能になりました。一代限りの身代であればこそ、身を捨てて皇帝のために尽力できたのですが、「家」を持てるようになれば、その「家」の繁栄こそ第一目的となります。
かくして、「宦官の孫」である曹操が天下を盗る下地ができあがりました。彼の「祖父」である曹騰(そうとう)は順帝の学友でもあった優秀な宦官でしたが、親戚の夏侯氏から養子を迎え、その子に家を継がせました。これが曹操の父親である曹嵩(そうすう)でした。
桓帝期に急激に大きな力を手にした宦官勢力は、次の霊帝期に入っていよいよ士大夫たちと正面衝突します。桓帝外戚の竇固(とうこ)と、士大夫階級の代表である太尉の陳蕃が手を組んで宦官を排斥しようとしますが、事前に計画が洩れて失敗。宦官たちがおこなった逆襲が、いわゆる「党錮の獄」でした。この時期になると、鄭衆や蔡倫のような、気骨と節度を持った宦官はほとんど居なくなり、それこそダーティな面ばかりが目立ちます。
霊帝の治世に、黄巾の乱が勃発します。かろうじて鎮圧には成功しますが、過分な褒賞を受けたのは宮中の宦官ばかりで、前線で戦った武人たちへの報酬が少なすぎたことが、三国の動乱の直接的な原因ともなりました。
霊帝は臨終に際し、信頼する宦官蹇碩(けんせき)に、第二皇子である劉協の擁立を命じたらしく、蹇碩は第一皇子の劉弁を推す外戚何進を殺害しようとしますが、失敗して逆に殺されます。なおこの蹇碩、叔父さんがパトロール中の曹操に夜間外出禁止令違反でとっつかまり撲殺されたことでも知られています。
何進は袁紹らの薦めで宦官を皆殺しにしようとしますが、これまた逆に先手をとられて殺されてしまいます。すると袁紹はすぐさま宮廷内に攻め込んで、何進大将軍の仇討ちと称し、本当に宦官の殺戮を開始します。どうも、袁紹は何進が殺されるのを待っていたように思えてなりません。何進は妹の七光りで大将軍にはなっていますが、ありようは肉屋の親父に過ぎず、士大夫階級の出身ではありませんでした。名門である袁紹にとって、何進ごときを見殺しにすることにはなんの痛痒も感じなかったでしょう。
この殺戮劇の最中、宦官張譲は劉弁と劉協の兄弟を連れて脱出しますが、何進が呼び寄せていた董卓(とうたく)の軍勢と鉢合わせして、逃げられないと観念し、仲間の宦官たちと共に川に身を投げて自殺するくだりは、三国志演義でもよく知られています。
張譲の自殺で、後漢王朝を傾けたに等しい宦官の勢力も、ほぼ壊滅しました。もはや世は武力の時代で、宮廷内でちまちまと工作するだけの宦官の出る幕ではなかったのです。
(2015.4.17.)
|