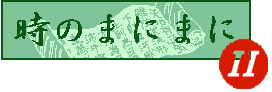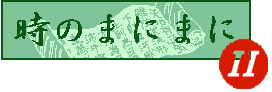|
宋王朝では、『水滸伝』のおかげで名を残した宦官童貫の他には、王朝をゆるがせるほどの害を為した宦官は見当たりませんでした。
続く元王朝は、基本的には遊牧時代の生活様式を失わなかったので、宦官が居なかったわけではないでしょうが、ほとんど重用された形跡がありません。
それでも、居なくなることはないのが宦官の凄みでもあります。元の次の明王朝は、後漢・唐と並んで宦官の害が甚だしかった時代として知られています。
明の始祖である洪武帝・朱元璋は、乞食坊主出身で、漢の高祖・劉邦と並ぶ成り上がり皇帝です。しかし劉邦がわりと最後まで生(き)のままで通したのに対し、朱元璋はなかなか勉強熱心で、歴史に学ぶのが好きだったようです。彼のすさまじいまでの功臣粛正は、ほかでもない劉邦が韓信や彭越、黥布といった功臣を殺したことに倣ったのだとも言われています。韓信たちは実際に謀反を企んだ(謀反を企まざるを得ないよう追い込まれた、とも言えますが)から誅殺されたのですが、朱元璋が粛正した臣下たちについては、ごく少数疑わしい者も居たにせよ、おおむね謀反を考えていたとは思えません。歴史に学んでも、独学の哀しさで、形ばかりを真似することになってしまったようです。
さて、朱元璋がもうひとつ歴史から得た教訓は、
「宦官を政治にタッチさせるな」
ということでした。彼は彼なりに、後漢や唐の歴史を読み、宦官が政治に口をはさみはじめるとろくなことにならないと喝破していたのです。
それで彼は、宦官と政治を切り離す法律を作りました。少しでも政治向きのことを口にした宦官は、むごたらしい方法で処刑されたのです。こうしておけば、何か嘆願がある者が宦官に贈賄して口を利いて貰おうなどと考えるわけもありませんから、宦官が権勢を持つようなことは決してあり得ない、と朱元璋は考えたのでした。
そのこと自体は、決して間違った考えかたではなかったと思います。実際、宦官が財力や権力を持つ道筋は、朱元璋が考えたとおりであったわけですから。
しかし、彼にはふたつほど見落としがありました。
そのひとつは、彼のような強烈な個性を持つ皇帝であれば、宦官に力を持たせないことは可能だったろうけれども、将来幼帝や愚帝が出現したとき、いわば「家族」である宦官に頼ってしまうことは充分考えられること。皇帝というのは基本的に孤独な存在で、その孤独に耐えられる強い性格を持つ人物が帝位に就くとは限らない、というか普通の人間にはなかなか耐えられないことでしょう。ついつい、身の回りの世話をしてくれている宦官に相談したくもなるというものです。太祖・朱元璋が禁令を出していても、そういう禁令はなし崩しに有名無実化するのが世の常です。
もうひとつは、宦官も人並みの感情を持つ人間であることを考慮していなかったことです。まあ、歴代の皇帝や士大夫たちは、もとから宦官という存在を蔑視していることが多かったので、やむを得ないことではありますが。
だいたいそんなに宦官が信用できないのなら、宮廷で宦官を用いることなどやめれば良さそうなものを、朱元璋といえども「後宮の管理は宦官の仕事」という固定観念から脱することはできなかったのでした。
朱元璋の歿後、皇太孫の建文帝が即位します。皇太子であった長男は朱元璋より先に死んでしまったので、そのまた長男を皇太孫として後継者にしたのでした。
建文帝は祖父の言いつけをよく守り、宦官に対する締め付けを続けました。
そのままであれば、明代にあれほど宦官が猖獗することはなかったかもしれません。
ところが、建文帝は致命的な失敗を犯してしまいます。
朱元璋には二十数人の息子が居ましたが、皇太子となった長男と、早死にした子を除いて、全員を王にしました。
皇帝が自分の息子を「王」に封じるのはよくあることですが、たいていは名前だけの王です。前漢の呉楚七国の乱とか、晋時代の八王の乱とかを教訓として、「王」たちにあまり大きな実権を持たせるべきではないというコンセンサスができました。少数の例外を除いて、中華帝国における「王」というのは、数県から1郡程度を「食邑」として持ち、そこからのアガリ(=年貢)で食っている宮廷貴族に過ぎません。
しかし、明初の「王」たちは実質的な「国」を持っていました。主に辺境ですが、それまでのたいていの「王」が、自分の「国」に赴任することすら稀であったことを考えると、徴税権・行政権・軍事権などを併せ持っていた彼らは、本当に小王国の国王にほかなりません。王朝を起ち上げたばかりの不安定な時期なので、朱元璋は息子たちに辺境の領地を与えて外敵を防ごうと考えたようです。臣下をまるで信用しなかった朱元璋ですが、息子たちなら決して裏切らないはずだと思ったのでしょう。
ところが代が変わって孫が帝位に就いてみると、それらの20近い「国」の王は、ほとんどが自分の「叔父さん」であるわけです。中には代替わりして「イトコ」が王であるところもあったでしょうが、叔父たちに取り巻かれているとなんとも居心地が悪かったようです。
そこで、王朝が安定して辺境も落ち着いたという名目のもと、建文帝とそのスタッフたちは、「王国」の取り潰しを策します。スタッフと言っても、有能な臣下を朱元璋が殺し尽くしてしまったため、二流の政客ばかりでした。
叔父たちにしてみると、辺境であるとはいえ「王国」は自分たちの領地です。それを有無を言わせず取り上げられるとあっては、不満が噴出するのも当然です。
朱元璋の四男である燕王は、やられる前にやってしまえとばかり兵を挙げます。朱元璋が首都を置いたのは南京でしたが、燕王は現在の北京附近、北の護りを担っていました。北には元がまだ健在です。
元王朝は中華帝国としては亡びましたが、これは実のところ、統治困難になった植民地を抛棄したようなもので、別に算を乱して逃げ出したというわけではありません。整然と北の草原へ帰っただけのことです。従って軍事的にも経済的にも、充分に余力を残しています。またいつ南下をはじめるかわかったものではありません。
こういう強敵と向かい合う北辺には、いちばん有能な息子を派遣し、強力な軍を率いさせようと朱元璋が考えたのも当然でした。その眼鏡にかなったのが、四男の燕王こと朱棣(しゅてい)だったのでした。
そのいちばん有能な叔父が、強力な軍を率いて南京に迫って来たので、建文帝の朝廷は震駭しました。
いくら強力な軍と言っても地方軍に過ぎず、兵力は圧倒的に南京側がまさっていました。ところが、それを率いて戦う優秀な将軍が居ません。これまた、謀反を恐れた太祖・朱元璋が殺し尽くしてしまっていたのです。残っていたのは二流の人物ばかりで、しかも建文帝は、その自信なげな将軍に対し、
──朕に叔父殺しの汚名を着せてはならぬ。
つまり燕王を殺すなという、なけなしの戦意さえしぼんでしまうような命令を出していたのでした。
それでも南京という城市は難攻不落の堅城として天下に名を知られており、どれほど下手に守っても数年は陥ちないはずでした。
ところが、燕王軍はあっさりと南京城内に侵攻してしまいます。
実は、洪武帝(朱元璋)・建文帝2代のあいだ圧迫され続けていた宦官たちが、ここぞとばかりに城門を開けてしまったのでした。陰湿な恨みの晴らしかたとも言えますが、圧迫がひどすぎて、こんな皇帝に仕えていては生命が危ないと思った者が多かったとも考えられます。
南京は燕王の手に落ち、建文帝は行方不明となりました。燕王は甥から簒奪した形で帝位に就きます。これが永楽帝です。
永楽帝は、その帝位奪取の過程で、宦官に助けられたため、親父の洪武帝の方針をあっさりくつがえし、宦官を重用するようになります。
朝野の人々が、自分を簒奪者と見ているのではないかという負い目もあったようです。実際、儒者の方孝孺は、永楽帝を祝福する文章を書けと言われて、ひとこと「燕賊簒位」と書いて紙を投げ捨てました。「燕王が謀反を起こして帝位を簒奪した」という意味です。方孝孺は即座に処刑されましたが、この事件が永楽帝に与えたトラウマは大きかったようです。
それなら、というので、永楽帝は士大夫に頼るのをやめ、宦官に大きな力を与えることにしてしまったのでした。その端的な例が、「東廠」の設立です。これは宦官による秘密警察で、永楽帝はこの東廠を使って、自分の悪口を言っているヤツが居ないかどうか調べさせたのでした。密告が大いに奨励され、その密告が嘘であっても罰せられないということにしました。イヤな時代の到来です。
当然、罪を逃れようと宦官に賄賂を贈る者も増えましたし、逆に東廠の力を振りかざして人々から金品を脅し取るような宦官も出てきました。宦官が跋扈する条件は充分に取りそろえられたわけです。
永楽帝が寵愛した宦官のひとりが、鄭和です。もとは辺境の少数民族の出身で、少年時代に戦争捕虜となり、去勢されたという経歴を持っています。眉目秀麗で、志操もさわやかな人物であったらしく、それで永楽帝も信任したのでしょう。
鄭和は、7回にも及ぶ西方への大航海をつつがなく成し遂げたことで有名です。航路自体はそれまでにも知られていたルートで、「大航海時代のさきがけ」とまで言うと褒めすぎかもしれませんが、巨艦を連ねて南支那海を、マラッカ海峡を、インド洋を往来した、海の男ならぬ海の宦官でした。穏和な中にも威厳のある人物で、当の海の男たちからも大いに信頼されていたようです。
鄭和がこれほど何度も大航海をおこなったのは、永楽帝から、行方不明の建文帝を探す密命を受けていたからだという噂もあります。建文帝が生きている限り、永楽帝は簒奪の陰口におびえなければならなかったのでした。
鄭和が建文帝を発見したという記録はありません。たぶん見つけられなかったのでしょうが、実は見つけて闇に葬った、あるいは見つけたけれどそっと見逃した、といった小説的想像もできないではない気もします。
鄭和本人はイスラム教徒であったようですが、14世紀という時代の人物としては、民族的・宗教的な偏見が非常に少なく、各寄港地でも評判は上乗だったと言います。稀に寄港地で武力衝突が起こることもありましたが、鄭和は軍事的な能力もあったようで、負けたことはなかったとか。紛争後の処理も手際が良く、各地で大いに徳とされた形跡があります。まさに、宦官にしておくのは惜しいほどの優秀な人物でした。
宦官の害が甚だしかったとされる後漢・唐・明に、共通する要素がもうひとつありました。その初期に、能力もあれば人格も高潔という、優秀な宦官が出現していることです。後漢では鄭衆や蔡倫がおり、唐では高力士が居ました。これらの王朝で宦官が重用されたにあたっては、彼らの余徳ということもあったように思えます。
明の場合はそれが鄭和でした。まあ、永楽帝はそれでなくとも宦官びいきではありましたが。
その後、明王朝期には前期に王振、後期に魏忠献というワルが出現したのでした。
中華帝国最後の王朝である清王朝期には、さほど宦官が目立ったことはありませんので、魏忠献などはさしづめ、「最後の悪宦官」とでも呼べそうです。その悪事もかなりスケールが大きく、秦の趙高と双璧という観があります。彼らについては、また稿をあらためたいと思います。
(2015.6.6.) |