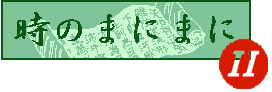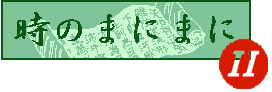|
小学生の頃からギリシャ神話などが好きで、何冊も子供向けの本を読んでいました。たぶん最初は、児童向けの世界文学全集などに載っていたいくつかのエピソードを読んだところから興味を持ったのであったと思います。それから学校の図書館などでも何冊か読んだのち、山室静氏が子供向けに書き下ろした「ギリシャ神話」を買って貰いました。そこそこ体系的な書きかたをしてある本で、オリンポスの12神などはそれで憶えましたが、数えかたにはいくつかの流儀があるようです。
子供向けですので、本来の神話に満ちあふれている近親相姦だの殺戮だのの毒気はだいぶ薄められていたものの、それでも繰り返し読み込んで、ずいぶんギリシャ神話に詳しくなったと思います。
すると同好の士というのは居るもので、クラスメイトのひとりと話が合い、一緒に新しい神話みたいなものを作ろうとしたこともありました。思えば、それを何年か温めて推し進めてゆけば、立派にいまで言うライトノベルの一本くらいは書けたような気もします。いささか時代が早すぎました。
さて、ギリシャ神話をしばらく堪能したあと、私は日本の神話にも興味を向けました。やはり外国の神話ばかりではなく、自国の神話を知っておきたいという気持ちが出てきたのです。
確か坪田譲治氏執筆による、やはり子供向けの「日本の神話」という本を買って貰いました。変な色がついておらずニュートラルな書きぶりで、導入としてはよくできていた本だったと思います。神代だけではなく、確かヤマトタケルの活躍くらいまでが書かれていました。なおエピソードのいくつかは、それまでに読んでいた昔話選集みたいな本にも載っていたと思います。
こちらの本も、私は何度も読みふけりました。
そのうち、子供向けの本だけでは物足りなくなり、もう少し詳しい本を読みたくなりました。小学6年生くらいの頃だったと思いますが、古本屋で「日本の神話」という本を見つけて、自分の小遣いで買ったところ、これがカッパブックスから出ていた高橋鐵氏の著作でした。高橋鐵といえば、言うまでもなく性科学研究の第一人者です。私はもちろん、当時そんなことを知りませんでした。日本の神話をフロイト的に読み解いて、そこに含まれている古代日本のおおらかなセックス観を解析しようという趣旨の本で、小学生にはさすがにどぎつ過ぎたかもしれません。何せ、なんでもかんでも全部セックスに結びつけて解釈しているのです。最初はよくわからなかったのですが、中学生になり、そっち方面の知識も着実に増えてきてから読み返してみると、
「うわ~~」
と叫びたくなりました。
こんな本を入口にして日本神話にアプローチしたのが、適当だったかどうかはわかりません。ただ、政治的やら思想的やらの立場から神話を云々することなく、神話を神話として純粋に愉しむということができたのは良かったと思います。高橋氏の「なんでもかんでもセックスシンボル」説は極端にせよ、古代の日本人が性について非常にあけっぴろげであることがわかり、神話における「性=生命」の躍動感については、ギリシャ神話などよりよほどヴィヴィッドなものがあると感じるようになりました。
大学1年の提出作品として書いた『オノゴロ島』という曲も、そういう気分の中で作曲したものです。この曲は雅楽の「序・破・急」の形式を援用しており、序の段はイザナギ・イザナミの両神が天の浮橋から海中に天沼矛(あめのぬぼこ)を挿し下ろし、引き上げた時に水滴が「こをろこをろ」と滴った場面をイメージしています。この滴った水滴が原初の大地「オノゴロ島」となるわけですが、だんだんと島の形態ができてゆくあたりを描いたのが破の段です。ここは雅楽の「越天楽」の変奏曲になっているのですが、審査した先生がたが気づいたかどうか。
急の段では、そうしてできあがった大地にさまざまな生命が繁殖してゆくさまをイメージしており、のちに私が自分の作品のグランドテーマとする「生命への讃歌」の萌芽にもなっています。
日本神話の冒頭に置かれた「国産み」の場面の、静謐から躍動への変容ということに惹かれて題材として扱っただけなのですが、友人のひとりはこれを
「右翼的」
であると評しました。ある程度、そういった感想が出てくることも予想はしており、やはりそんなことを言う手合いが居たか、という程度の気分でしたが、神話そのものに右も左もあるものか、という確信は余計に強まりました。
『オノゴロ島』を書いた頃には、すでに「古事記」も読んでおり、楽譜の表紙にその一節をエピグラフとして引用しておいたりもしています。
ただし「記紀」と併称される「日本書紀」のほうを読んだのはだいぶあとのことになります。「古事記」は「物語」であり、「日本書紀」は「史書」であるということで、やはり古事記に較べてだいぶ読みにくかったのです。
日本書紀が「史書」である、と言われると、首を傾げる人も少なくないかもしれません。戦後史学界では、記紀というのは
──天皇制を正当化するために書かれた政治文書である。
という見かたが大手を振ってまかりとおり、ほとんど定説みたいなことになってしまっていたからです。左翼系の学者ばかりでなく、中道くらいの人でも、いくぶん疑問符をつけながらとはいえ、「政治文書」説に賛成するケースが多かったようです。これに反対するヤツは右翼であると、そんなに簡単なものではなかったかもしれませんが、見た限りではそういう空気があったように思えます。
しかし、色眼鏡をかけずに真摯に日本書紀と向き合えば、これが「政治文書」であるなどというのはどう見ても言いがかりだとしか考えられないのです。
まず、「誰に向かって正当化しているのか」という点が定かではありません。よく言われるのが「唐に対して」という意見です。当時の天下王朝とも言えた唐に対し、わが国にもこんな立派な史書があるのだと主張すると共に、天皇家の正統性を唐の皇帝に認めて貰うために書かれたというわけです。
しかし、この説には致命的な弱点があります。記紀は確かに漢文をベースにして書かれてはいますが、中国人が読んで理解できるようにはなっていないのです。とりわけ古事記において顕著ですが、例えば無数に挿入された歌は、すべて漢字に音だけ借りた日本語そのものによって書かれており、中国人が読んでもちんぷんかんぷんでしょう。唐の人士に読ませるためであれば、こんな書きかたをするはずはありません。その時代の日本人は、阿倍仲麻呂がそうであったように、唐に行って高官に出世するほどの知識と人格を備えた者が何人も居り、立派な漢文を書く能力は充分にありました。現に太安万侶による古事記の序文は、見事な四六駢儷体(べんれいたい)によって書かれています。四六駢儷体は、南北朝から隋唐にかけて流行した、華麗な修辞を伴った漢文のスタイルであり、当時の日本の知識人はこれを充分に使いこなしていたのでした。
ですから、記紀が唐に対するアピールであったのであれば、必ずや唐の人士に完全に理解される書きかたをしたはずであり、できたはずなのです。
では「国内の豪族に対する正統性の主張」ということならどうでしょうか。
記紀が書かれた時代は、すでに天皇家を凌駕するほどの大豪族は姿を消しています。古くは葛城氏、大伴氏、物部氏、そして蘇我氏などといった対抗勢力がありましたが、蘇我氏本流の稲目→馬子→蝦夷→入鹿という系統が亡ぼされたあとは、どの豪族も天皇家にあらがえるほどの実力は示せなくなりました。そういった古代豪族に代わり、藤原氏が擡頭しはじめてはいましたが、藤原氏は武力というほどのものを持たずに、むしろ天皇家に密着することでみずからの権能を高めるという方法を採り、共存共栄を図りました。
天皇家内部の争闘(壬申の乱)もひとまず終熄し、国内的には一安を得た時期であったからこそ、史書をまとめるという機運も出てきたのでしょう。そこで高らかに天皇家の正統性を謳い上げ、臣民どもに示すために書かれたのが記紀である……という見かたは、確かにある程度説得力を持っています。
しかし、よく考えればこれもまたおかしいのです。
以下のことについては、何度か触れたことがありますが、日本書紀には随所に
──一書に曰く
というフレーズが登場します。
冒頭の国産みのあたりなど、「一書に曰く」がいきなり6つか7つくらい並べられています。
いちばん大事な「国の創造」を記した部分に、6つ7つといった「異論」が併記されているのです。こんな「政治文書」がどこの世界にあるものでしょうか。
政治文書どころではありません。こんな書きかたをしている「史書」も、近代以前にはほとんど存在していないのです。
史書というのは、書かれた時代から見ても古い時代を扱うものですから、当然ながら事実関係やその解釈にいくつかの説が生まれています。史書を執筆する史家は、それらの説のうち、自分の好み──と言って悪ければ合理性が納得する説をひとつ選んで、歴史をひとつのストーリーとして紡ぎ上げます。そこには捨てられた史料や異説が累々として横たわっています。司馬遷もトゥキディデスもイヴン・バトゥータも、みんなそういう姿勢で歴史を綴っています。
いろんな史料を渉猟し、それらを公平に併記して後学の史料批判に資するなどというのは、歴史学というものが精密化した近代以降の記述方法です。日本書紀は、その点では科学的と言ってよいほどです。少なくとも7~8世紀という時点で考え得る限りの「公正な歴史書」を作ろうとしたことは間違いないように思われるのです。
天皇家にとって都合の悪いような記述もちょくちょく出てきます。武烈天皇の項など、罪人の手指の爪を引きはがしてイモを掘らせたとか、妊婦の腹を割いたとか、これでもかと言わんばかりのとんでもない暴君ぶりを活写しており、それゆえ武烈天皇とその次の継体天皇とは関係がなくここで王朝交代があったのではないか、などとも言われているわけですが、それにしても万世一系を主張するなら都合の悪い記述であることに変わりはありません。古事記のほうには武烈天皇の事績はほとんど書かれていません。
偉大な「大王(おおきみ)」であったとされる応神天皇や雄略天皇についてさえ、けっこう傍若無人な独裁者ぶりを髣髴とさせる記述があり、編者が歴史上の天皇についてきわめて冷徹な眼で眺めていることが感じられます。編集委員の中には当時の皇族の長老とも言える舎人親王が居たのですから、不都合な記述を改めさせようと思えば改めさせることもできたはずなのですが、おそらく「真実の歴史を記載しようではないか」という編集方針に賛同して黙っていたものと思われます。
日本書紀は、近代以前の書物としては、世界的に見ても類例がほとんど無いほどに誠実で真摯な姿勢で編纂された、きわめて良質な「史書」であると私は思っています。これを「政治文書」などというのは、日本の歴史そのものを貶めんがための言いがかりであると断言して良いでしょう。
異論を併記した近代以前の史書などほとんど無い、と書きましたが、実はひとつだけあります。「三国志」がそれです。
よく知られていますが、三国志は陳寿という人物が執筆しました。この人がまた、近代人顔負けと言って良いほどに厳密な史料批判をおこなう人で、いやしくも疑わしい話はことごとく却下し、まず確実と思われることのみを記述しています。後世、軍略の神様みたいな扱いになった諸葛孔明についても、きわめて冷徹かつ公正な見かたで書いています。陳寿自身が蜀の国に生まれた人物であったらしいので、
──陳寿の父親は馬謖(ばしょく)の属官であった。諸葛孔明の第一次北伐の際、馬謖は孔明の指示を無視して大失敗を犯し、大敗する。孔明は敗軍の責任をとらせて馬謖を処刑する(「泣いて馬謖を斬る」の成語になりました)。この時、陳寿の父親も馬謖に連座して処罰された。そのため、陳寿は諸葛孔明に含むところがあったので、「三国志」の中で貶めて書いたのだ。
というような俗説がささやかれていたほどです。しかし近年の研究では、陳寿の孔明評は非常に正鵠を射ていたという評価になっています。
ともかくそんな姿勢で、疑わしい話を片端から切り捨てたため、「三国志」本文の記述は著しく簡潔すぎて、あんまり面白くないものになっています。
そこで註釈を加えたのが、陳寿より100年ほどあとの裴松之という人でした。彼は三国時代を扱った書物を、手に入る限り集め、その中でわりと信憑性のありそうな話を註釈として付け加えたのです。
その後の三国志のテキストは、陳寿の本文と、裴松之の註釈が両方書かれたものとして流布しました。読んでいると、至るところに「松之曰」というフレーズが登場します。陳寿の本文に対して異説を紹介すると共に、その出典も明記してます。つまり三国志は、ふたりがかりとはいえ、異論を併記した形になっている稀有な史書なのです。「三国演義」をはじめとして三国志の物語が他の時代より好まれるのは、登場人物の魅力もさることながら、原典に異論が併記されているおかげで、多様な解釈が可能であるためではないかと私は考えています。
さて、日本で史書を編纂しようとなった時に、当然ながら中国の正史が参考にされたことでしょう。当時としては史書のモデルはそれしか無かったので、仕方がありません。当然、入手できる限りの正史を集め、どういう記述方法が良いか検討されたはずです。
当時日本で入手できたであろう中国の正史は、「史記」「漢書」「後漢書」「三国志」「晋書」「宋書」「南斉書」「魏書」というあたりでしょうか。もしかしたら「南史」「北史」あたりも入手できたかもしれません。これらは慎重に吟味され、比較検討されたと思われます。
この中で、編集委員たちは「三国志」を選んだのだと思います。内容があまり多方面に拡がっておらず構成がシンプルであること、そして異論併記がなされて大変公正な記述に見えたことが大きかったでしょう。まさに慧眼でした。
そして書名は、内容が中国の史書で言うところの「本紀」だけみたいなものだったので、「書紀」の文字を用いたのでしょう。もしかすると「日本・書紀」ではなく「日本書・紀」だったのかもしれません。日本書(=日本の歴史を誌した書物)の中の紀(帝王の事績を記した部分)というつもりであった可能性もあります。中国の史書にはこの他、「伝」「表」といった部分が含まれる場合が多く、日本でも日本書紀の続編というか第二期刊行として「日本書・伝」なんかが計画されていたけれども何かの理由でポシャってしまったのではないか……など、想像は拡がります。
ともあれ、7~8世紀という時期の日本人を、近現代という立場からあまり舐めないほうが良いというのが、かねてからの私の意見です。庶民はともかくとして、少なくとも当時の知識層は充分な合理を身につけており、あやしげな呪術などが威をふるっていた時代だとはどうも思えないのです。むしろ平安時代に入った9世紀以降のほうが迷信や呪術などに左右される面が大きく、これは日本だけでなく、世界的にも中世という時代区分に特徴的な現象と言えます。
記紀を読んで変だと思ったことがあれば、当時の知識層はすぐに反応したはずです。記紀が「天皇制を正当化する政治文書」などであったとしたら、たちまち見抜かれてそっぽを向かれたことでしょう。「自分が伝え聞いていたストーリー」とほぼ一致していたからこそ、これらの書物は多くの人々に受け容れられたのです。
記紀は、日本人が最初に持った、輝かしい人文成果であることに。疑問の余地はありません。
(2015.1.17.) |