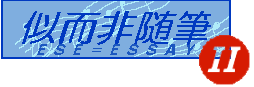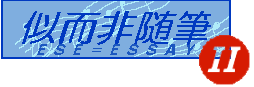|
「ダフィット同盟」なるものをご存じでしょうか?
ダフィットはダビデのドイツ語読みです。英語ではデイヴィッドという名前になります。ダビデとはむろん、旧約聖書に登場する古代イスラエル王国の王様のことです。
旧約聖書によれば、ダビデはもともと羊飼いでしたが、当時のイスラエル王サウルに召し出されて戦士となり、イスラエルと敵対していたペリシテ人の軍勢を幾度も打ち破りました。あまり活躍したためにサウル王に妬まれ、何度も殺されかけますが、「神の恩寵がサウルから去っていたため」その都度逃れました。ダビデはサウル王に執拗に生命を狙われながらもサウル王への忠誠を持ち続け、何度かサウル王を殺す機会があったものの毎回見逃しました。
やがてサウル王は自ら率いた軍勢でペリシテ人の軍と戦って大敗し、自害します。その息子らもほとんど戦死します。生き残った息子のひとりイシュ・ボシェトは、南のユダの王に推戴されたダビデと何度も戦いますが、臣下に暗殺され、ここにダビデはユダとイスラエルを合わせた広域の王となったのでした。
古代イスラエルの全盛期を到来させた偉大な王様とされています。
上位者に何度も殺されかけながら恨みを抱かなかったというあたりは、中国の伝説的な帝王である舜のエピソードを髣髴とします。舜も、盲目の父に何度も殺されかけつつ、父への孝心を最後まで失わず、父が死んだときにはさめざめと泣いたと伝えられます。このあたりはまあ、だいぶ美化されていると考えて良いでしょう。
しがない羊飼いから抜擢されたと言っても、まったくの庶民であったとは考えられません。これまた古代中国で言えば、羌(きょう)族のような、牧畜をなりわいとする種族の長だったのではないでしょうか。羌族からは、ダビデとかなり近い時代に、太公望という天才戦略家が出ています。太公望は周の文王とその息子である武王に仕えて、当時の天下王朝であった殷を打倒しました。ダビデもそんな形でサウルに仕えたのだと思われます。イスラエル人がみな怖れていたペリシテ人の猛将ゴリアテを斃すという大殊勲を上げて名を挙げました。ゴリアテは「巨人」ということになっていますが、まあ雄偉な体格をしていたのでしょう。
太公望は最後まで周王の臣下として生涯を終えましたが、ダビデはおそらく、サウルにいちど斥けられたのちに、南のユダ族を糾合し、サウルの後継者に幾度も戦いを仕掛けてついに勝利し、イスラエル全土を支配下に置いたというところだと思います。
ダビデの実像の推測はこのくらいにしておきますが、聖書によるダビデの人物像としては、もうひとつ、音楽に堪能だったらしいという一面があります。ダビデがサウルに召し出されたいきさつも、音楽に関わっています。
アマレク人との戦いに際して神に背いたサウル王は、神の恩寵を失ったため、夜ごとに悪夢に苛まれるようになります。家臣たちは王様の身を案じ、竪琴の巧みな者を側に置くことを進言します。それで召されたのがダビデだったというのです。ダビデがサウル王の近くで竪琴を弾くと、サウル王の気分は落ち着き、心安らかに眠れるようになったそうです。
また旧約聖書の「詩篇」の多くがダビデ作とされています。詩篇はこれも中国の「詩経」同様、本来はメロディーをつけて歌われたものですから、ダビデの作詞作曲ということになるでしょう。現在の研究ではダビデ作ということの事実性はほとんど否定されていますが、ともかく詩にすぐれ、音楽にすぐれていたというのがダビデの伝統的な人間像だったわけです。
さて、そのダビデの名を冠した「ダフィット同盟」ですが、これは国家間の連合とか政治結社とかそういったたぐいのものではありません。
音楽史上のタームです。
新しい思潮の音楽を掲げる人々が盟に加わり、ペリシテ人になぞらえた旧弊固陋なやからを打倒しよう、というのがこの同盟の趣旨です。
ところが、こんな名前を称した音楽家グループがある時期活躍していた、という史実も無いのでした。
それもそのはず、「ダフィット同盟」とは、ある一個人の脳内だけで結成された、架空の党派に過ぎないのです。
その一個人とは誰あろう、ドイツ・ロマン派の旗手として知られるロベルト・シューマンその人でした。
シューマンの実家は書店を営んでいて、彼は本の香りの中で育ったと言って良いでしょう。たいへん読書家でもありました。
親の意向もあって当初は司法官を志し、ライプツィヒやハイデルベルクの法科大学に入って勉強しますが、音楽への情熱もだしがたく、大学を中退してフリートリヒ・ヴィークの内弟子となります。このヴィークの娘が、のちにシューマンと結婚したクララです。
よく知られているように、シューマンは自分の考案したピアノ練習用の装置のために指を傷め、ピアニストとしての道を諦めました。それで、作曲家兼音楽評論家という道を歩むことに決めたわけです。豊富な読書体験により、文才にも恵まれていたので、当時刊行されていた「ライプツィヒ音楽新報」という雑誌に、しばしば論文が掲載されるようになっていました。最初に掲載されたのが、ポーランドの片田舎からパリに出てきたばかりの若い作曲家ショパンを論じた文章で、
「諸君脱帽したまえ、天才の出現だ!」
という一節はいまなお語りぐさになっています。パリデビュー間もないショパンにとっても、この論文はありがたい援護射撃となったことでしょう。なおここでシューマンが論じたショパンの作品は、作品2の「モーツァルトの主題による変奏曲」であったようです。「ドン・ジョヴァンニ」の中の二重唱「La
ci darem la
mano(お手をどうぞ)」を主題としたピアノとオーケストラのための変奏曲で、今日ではほとんど顧みられることのない作品です。この曲をもって「天才の出現だ」と断じたのは、かなり強引であったかもしれません。
この雑誌に、シューマンは次々と評論を発表するのですが、ある時期からペンネームを使うようになります。それも2通りの名前を使い分けます。ひとつがフロレスタン、もうひとつがオイゼビウスという名前で、フロレスタンは活溌で行動的、オイゼビウスはもの静かで瞑想的というキャラ付けがされました。このどちらかの名前で論文を書くこともあれば、ふたりが対談していたり、他のメンバーも加わって座談会を開いたりといった体裁でシューマンの自説を開陳するということもおこなわれました。
なかなかアイディアマンであったことが伺われますが、見かたによればかなり子供っぽい所行でもあります。
そしてこのフロレスタンとオイゼビウスを含む「新しい音楽」の担い手たちが加わった──というよりシューマンが脳内で加えたグループが「ダフィット同盟」であったのです。
ダフィット同盟は、ライプツィヒ音楽新報紙上だけのお遊びにとどまらず、シューマンの作曲活動にもその設定が適用されはじめます。
シューマンの初期の作品は、作曲順序と作品番号がいささか混乱していて、必ずしも作品番号順に作曲されているわけではありません。
しかしとにかく、作品1(アベッグ変奏曲)から作品23(4つの夜想曲)まではすべてピアノ曲となっています。作品24から急に歌曲が作られはじめますが、これははっきりとクララとの結婚が契機となっています。つまり、結婚が決まるまでは、クララの気を惹き続けるためにピアノ曲ばかり書いており、決まった途端に他のジャンルの曲を書き始めたということです。なお作品26(ウイーンの謝肉祭の騒ぎ)作品28(3つのロマンス)作品32(4つの小品)も、実は結婚の前年までに作曲されていますので、何やら露骨に「釣った魚にエサは要らない」という言葉を地で行っているようでもあります。それ以後の主なピアノ作品となると「若い人のためのアルバム」と「森の情景」くらいなものですので、いかに彼のピアノ曲と求愛行動がリンクしていたかわかろうというものです。
さて、その中で「ダフィット同盟」の設定がはっきりと顕れているのが、作品6「ダフィット同盟舞曲集」と作品9「謝肉祭」です。どういうわけだか、「謝肉祭」のほうが作曲も出版も先になっています。
この他にも、例えばソナタ第1番は「クララへ、フロレスタンとオイゼビウスより」と献辞がつけられていますし、幻想曲も最初は「フロレスタンとオイゼビウスによる大ソナタ」と題されており、ダフィット同盟がらみの作品は相当多数に及ぶと考えられます。
順序からしてまず「謝肉祭」を見てみます。20曲の小品から成る、かなり大がかりな組曲ですが、まず第5曲が「オイゼビウス」と題されています。続く第6曲が「フロレスタン」となっています。第11曲が「キアリーナ」で、これはクララの愛称。第12曲には「ショパン」が登場します。第13曲は「エストレッラ」これは本名をエルネスティーネ・フォン・フリッケンという女性で、この時期のシューマンの恋人でした。
──おいおい、クララひと筋じゃなかったのか?
と言いたくなりますが、実のところシューマンは少々むら気なところがあって、後年もクララの父ヴィークに出禁を食らったりして疲れ果てたのか、他の女性にちょくちょく関心を移していることがあります。一途に愛を貫いたのはむしろクララのほうだったようです。また、「謝肉祭」作曲当時はクララは16歳で、シューマンもまだ彼女のことを本気で結婚相手として考えるには至っていなかったと思われます。なお、エルネスティーネの父のフォン・フリッケン男爵は、アマチュアのフルート奏者で作曲もし、その作品がシューマンの「交響練習曲」の主題に使われています。
「謝肉祭」に話を戻すと、第16曲「ドイツ風のワルツ」の中間部には「パガニーニ」と題された部分が登場します。そして終曲は「ペリシテ人たちを討つダフィット同盟の行進」と、露骨なタイトルになるのでした。
つまりシューマンの脳内では、自分の分身であるフロレスタンとオイゼビウス、それに当時は妹分みたいな存在であったろうクララ、恋人エルネスティーネ、畏友ショパン、尊敬するパガニーニ(シューマンの作品3と作品10は「パガニーニのカプリチオによる演奏会用練習曲」第一集・第二集となっており、彼がこのヴァイオリンの鬼才に非常に傾倒していたことは確実です)などが、ダフィット同盟のメンバーとして設定されていたのでしょう。この時点ではおそらく、クララの父ヴィークや、エルネスティーネの父フォン・フリッケン男爵もメンバーに数えられていたに違いありません。
勝手にメンバーにされていたショパンなどがどう思ったか、コメントが残っていないのでわかりません。苦笑して「彼らしいなあ」とでも言ったような気がしますが。
「ペリシテ人たちを討つダフィット同盟の行進」では、シューマン自身が作品2「パピヨン」終曲で引用した古い舞曲「おじいさんの踊り」のメロディーを旧弊な「ペリシテ人」の象徴と見なし、重低音で吼えまくるこのメロディーをダフィット同盟のメンバーたちが寄ってたかって押さえ込み、勝利の凱歌を揚げる……というカッコ良いストーリーに基づいて曲が構成されています。聴いただけでも充分ストーリーがわかるような書きかたがされているのでした。
そして「ダフィット同盟舞曲集」、こちらは初版では作曲者名そのものが「フロレスタンとオイゼビウス」になっており、曲によって「F」あるいは「E」のイニシャルがつけられていました。そして、2部に分かれたこの小品集において、それぞれの部の最後の曲には、何やら思わせぶりな文章も書き加えられています。第1部では
「ここでフロレスタンは口をつぐみ、その唇はいたましく震えた」
第2部では
「まるで余計なことだったが、オイゼビウスは次のような想いをめぐらせた。そのとき、彼の眼には多くの至福が現れたのだった」
おそらく、この曲集でもシューマンは、なんらかの「裏ストーリー」を設定していたように思われます。
架空の人格や組織を夢想し、そこに自分の友人知人を取り込み、架空の敵と戦い、それを空想するだけではなくけっこう実際に書く文章その他に反映させる……というのは、いまで言うと「中二病」と称される傾向に非常に近い気がします。中学2年くらいの、何事にも背伸びしたい言動を指した、自虐ないし揶揄の言葉が中二病であって、別に治療を要する病気や精神疾患というわけではありません。もともとネットスラングですが、最近ではライトノベルなどで普通に使われています。
シューマンという作曲家は、ある時点までかなり重度の中二病であったと考えると、フロレスタンとオイゼビウス、あるいはダフィット同盟といった稚気あふれる「設定」が理解できるような気がします。もちろん彼がこういう「設定」を弄したのは中二どころか20代のことですが、それは彼の生きた19世紀と現代との、情報量の差というところかもしれません。
中二病的言動というのは、年月が経って振り返ってみると、布団を抱えて部屋の中をゴロゴロと転げまわりたいような羞恥を覚えたりするものですが、実はシューマンにもその傾向があります。
「ダフィット同盟舞曲集」は、ずっと後年に改訂版が出たとき、シューマンはフロレスタンとオイゼビウスの名をイニシャルを含めてすべて消去し、上に紹介した思わせぶりな文章も削除しました。ソナタや幻想曲その他の譜面に附記されていたフロレスタンとオイゼビウスの名前も、のちに改版するときには全部外しています。本当は「謝肉祭」の各タイトルも消したいところだったかもしれません(特に「エストレッラ」はクララの手前気まずかったでしょうから)。
要するにあとから振り返ってみて、若い頃の「ダフィット同盟」設定が、黒歴史にしたいくらい羞しかったのではないかと思われるのです。現代流布しているシューマンの初期作品の曲目解説などが、漏れなく「フロレスタンとオイゼビウス」や「ダフィット同盟」に触れているのを知ったら、あの世のシューマンはじたばたしながら
──頼む、後生だからやめてくれえええ!
と叫び出すのではないかと、私はついニヤニヤしてしまうのでした。
(2015.11.3.)
|