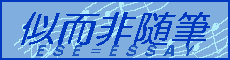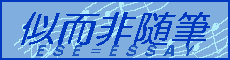|
「マイ・フェア・レディ」というミュージカルがある。「踊り明かそう」「運がよけりゃ」「君住む街で」など数々のヒットナンバーで知られるロングランミュージカルである。
このミュージカルの原作は、今世紀初頭、辛口の文明批評で名をはせたバーナード・ショウの「ピグマリオン」という小説だ。ピグマリオンは言うまでもなく、自ら彫刻した女性の像に恋してしまったキプロスの王である。ショウはこの伝説を、言語学者とロンドンの下町娘に投影して描いたのであった。
ある言語学者が友人と、ロンドンのイースト・エンドの下層階級の娘を、教育によって上流の淑女に変身させることができるかという賭けをする。彼は娘を辛抱強く訓練し、見事賭けに勝つのだが、いわば自分で作り上げたこの娘に、彼自身が恋してしまうというのが大体の粗筋だ。
われわれはなんとなく、がさつな娘と偏屈な老学者の、風変わりなラブコメディとしてのみ「マイ・フェア・レディ」を見てしまう。しかし、この物語は実はとんでもない毒を含んでいるのである。
そもそも、こんな賭けが成立する背景を考えてみなければならない。当時のイースト・エンドといえば、阿片窟や売春宿の立ち並ぶ、最悪のスラムである。新宿の歌舞伎町みたいなものかと思うかもしれないが、そんな甘いものではない。
何より、使われている言葉(コクニーと呼ばれる)からして違う。隠語や方言といった程度の問題ではない。例えばわれわれが英語の授業で四苦八苦した三単現などここにはないし、発音もめちゃくちゃなのだ。
実は、英語にはもともと標準語というものはないらしい。クイーンズ・イングリッシュと呼ばれているのは、ジェントリー(郷紳)階級の言葉であるに過ぎない。階級によって発音は愚か、文法まで変わってしまうのが英語という言語なのである。
厳密な意味での階級制が、過去もほとんどなかった日本人には、なかなかわかりずらい。士農工商があったじゃないかと言われるかもしれないが、あれは単なる身分(ステータス)の違いに過ぎず、階級(クラス)と称せられるべきものではない。武家言葉などあるにはあったが、例えば農家の息子が士分に取り立てられて武士になれば、別に厳しい教育を受けなくても、その日から武家言葉を使うことができたのである(新撰組の連中を見よ)。こんな国では、女主人公イライザの悲劇がどれほどのものであるか、わかりようもない。
英国に限らず、ヨーロッパ人にとって、階級が違うというのは、人類としての進化の度合いが違うと言うに等しかった。少なくとも今世紀初めくらいまではそうであった。言葉が違うくらいは当然である。その、どうしようもないほどの壁を、教育の力だけで打ち破れるのか……ヒギンズ教授の賭けはそういうことだった。
そう考えてみれば、イライザが受けたのはいわば人間の改造に他ならない。「丁寧な言葉をしつけられた」どころの話ではないのである。
結果、彼女の人間改造は成功し、上流階級の言葉を操るようになる。しかし、そこまでなのだ。調べれば彼女が本当の上流階級(エスタブリッシュメント)でないことはすぐわかる。当然、その社会に融けこめるわけはない。
だが、もっと悲惨なのは、彼女はもう、もとの社会にすら戻れないと言うことなのだ。使う言葉が違ってしまったからである。わが国の武家言葉のごとく、簡単に身につけたり捨てたりできるものではない。とにかく文法からして違うのだ。
イライザは、一旦飛び出した教授のもとへ、最後に帰ってゆく。これは色恋の問題ではない。下層階級でもなく、上流階級でもない、いわば奇妙な「階級のキメラ」となってしまった彼女には、もはや自分を改造した責任者の所以外、帰るところがなかった。教授の賭けは、ひとりの娘のアイデンティティを破壊するという、残酷な結果に終わったのだ。
教育によって人間を向上させることはできるが、その前に階級制度を改めない限り効果がないというのが、この小説におけるショウの主張だと思われる。
こういう重いテーマの小説がラブコメになったのは、ミュージカルに仕立てたアメリカ人にも、日本人と同じく階級観念というものがあまりなかったからであろう。
なお、現代のロンドンは、さすがに教育が普及して、あのおそるべきコクニーもほぼ廃れつつあるという。英国の名誉のために付言しておく。
|