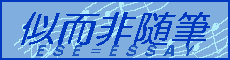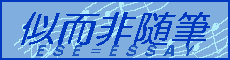|
小林×星氏と服部×久氏の間に盗作騒ぎがあったのは記憶に新しい。騒ぎは法廷へ持ち込まれ、盗作だ、いやたまたま似てしまっただけだという双方の主張が繰り返された。判事も裁定に苦慮し、とうとう「双方の作品に共通している音符の個数」を数えるなどという不毛な作業を始めてしまった。
裁判所のやり方もお間抜けだが、これは必ずしも責められない。判事は音楽の専門家ではないのであって、それ以外に客観的な判定の方法が考えつかないとしても無理はないのである。いや、専門家であっても、「客観的な判定」などできるものかどうか疑わしい。
似ているメロディーがあった場合、それがたまたま似たのか、一方が一方を盗用したのかという判断は、そう簡単にできるものではないのである。
有名な例だが、モーツァルトの「五月の歌」と中田章の「早春賦」と森繁久彌の「知床旅情」の冒頭のメロディーは非常によく似通っている。いずれも3拍子系の同じリズムで分散和音を奏するという形になっており、よく冗談のネタになる。林光は合唱編曲集『日本叙情歌』の中の「早春賦」の間奏に臆面もなくモーツァルトを引用したし、かく言う私も以前に「五月の歌」を編曲する時「早春賦」と「知床旅情」を引用して笑いをとった。
作曲された順序から言うと、モーツァルト、中田、森繁ということになるが、それでは中田章がモーツァルトのメロディーを盗用し、森繁久彌が中田のメロディーを盗用したのかと言えば、そうではあるまい。三人はまったく独立してこのメロディーを考えついたに違いないのである。自分の情念にいちばんふさわしい旋律型を考えたらこうなっていたということだろう。
とはいうものの、完全に無関係かと言えば、そうも言いきれないのが厄介なところで、以前に聴いたモーツァルトの旋律が頭の中のどこかに残っていて、無意識にそれと似た旋律を作ってしまったということも充分に考えられる。この場合、無意識を介した盗用ということになってしまうのか。
無意識の構造はまだよくわかっていないので、一旦無意識に沈潜したものが出てきたからと言って盗用とは呼べない、という人も居よう。一方、無意識だろうとなんだろうと盗みは盗みだ、という厳しい人も居ることだろう。盗癖のある人は無意識のうちに他人のものをポケットに入れてしまう。情状酌量や精神鑑定で無罪になるかもしれないが、盗難の事実は事実として残っているではないか。
ただ物財の盗難と異なるのは、盗まれた人間が、盗まれたものを失うわけではないという点で、これがまたややこしさを産んでいる(実は失う場合もある。これについてはあとで述べる)。
似通った例というのはこればかりではない。ショパンの「幻想曲」の3小節目からが、中田喜直の「雪のふる町を」とそっくりだとか、ベートーヴェンの第12番のピアノソナタ終楽章の途中から「証成寺の狸囃子」が出てくるとか、やはりショパンの「英雄ポロネーズ」の中間部分のバス進行が「ウルトラセブン」みたいだとか、探せばまだまだ見つかるのではないかと思う。
「音楽は、有限の音の組み合わせなのだから、たまに似たものができても仕方がない」という人も居る。「有限の音の組み合わせ」というところは確かに事実である。ただ組み合わせの数は天文学的数字となり、何万人の作曲家が寄ってたかったところで網羅できる数ではない。しかし、音楽として意味のある組み合わせとなるものはその中でも限られているから、「似たものができても仕方がない」というところは、弁護者の意見としてはこれまた正しい。作曲家自身が言い訳にするのは少々困るけれど。
ともあれ、Aという曲の一部分とBという曲の一部分が似てしまうということは、さほど珍しいことではないのであって、そういう一瞬の類似をあげつらっていると、はっきり言ってきりがない。こういうものをすべて盗作だなんだと言い出せば収拾がつかなくなる。
以上は無意識に「似てしまう」場合なのだが、それでは意識していた場合はどうか。
意識的に盗用したならばこれは弁解の余地がない、と思われるかもしれない。
だが、西洋音楽というのはもともと、ある程度自己完結したサークル内での営みだった部分がある。近代以前のことではあるが、まあ大雑把に言って教会・宮廷・都市といったあたりがそのサークルを作っていた。
そういうサークルの中で、モティーフの借用といったようなことはわりに普通におこなわれており、別に非難される振る舞いではなかった。
例えばルネサンス期には、教会で歌われるミサ曲に、世俗音楽のメロディーを採り入れた、いわゆるパロディ・ミサが流行した。われわれはジョスカン・デ・プレ、パレストリーナ、ラッススといった大作曲家たちの宗教音楽を聴きながら、実は15〜16世紀の流行歌に接している場合が少なからずあるのである。これは喩えて言えば、松村禎三がつんくのメロディーをそのまま作品に借用するようなものであって、今の感覚からするととんでもない話だ。しかし、当時はそれが盗用などという感覚はなかった。
宮廷の中などでは余計にサークル性が強かった。考えなければならないのは、その頃の作曲家はゲイジュツ家などではなく、雇い人であり、職人だったということである。雇い主に
「このメロディーを使って一曲作ってみよ」
と命じられたら、否も応もなく従わなければならなかった。それが他人の作ったメロディーでも、そんなことは関係ない。
バッハのオルガン協奏曲(「オルガンとオーケストラのための曲」ではなく、「オルガンで協奏曲のような効果を出した作品」である)のいくつかはヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲をアレンジしたものである。現在ではバッハがヴィヴァルディの作品を「編曲」したもの、と理解されているから、バッハを非難する人は居ないわけだが、本当にそうだったろうか。バッハは「自分の作品」としてオルガン協奏曲を世に出したのではなかったか。当時、作曲と編曲はそんなにきっちり区別されていたろうか。疑えば疑える。
他人のテーマを用いて即興演奏するなどということはしょっちゅうおこなわれていた。バッハだっておそらく、
「じゃあ今日は、ブクステフーデのソナタのテーマで何か弾いてくれないか」
というような要求に日々応えていたであろう。
作曲家の作品は、その作曲家の私物ではなく、いわばサークル内での共有物となっていたのだと思われる。
こういう環境であれば、自分の作品に他人のテーマやモティーフを借用することに、別に罪悪感は覚えないだろうし、借用された方もさして気にしないだろう。むしろ、
「おれの曲のテーマは、もう5人の同業者が使ったぞ。どうだ、すごいだろ」
と威張るほどではなかったか。
古い時代の作曲家の作品で、真作偽作が問題になることが多いのは、こういう習慣があったせいでもある。
古典派の時代になると、かなり作曲家のオリジナリティが認められるようになってくるが、それでも他人のテーマを拝借するということはまだ珍しくなかった。ただ、その場合でも、そのテーマを使っていかにオリジナルな展開をおこなうかという点に重点が置かれるようになったのは確かだ。流行しているオペラのアリア(当時の感覚としては、映画やTV番組の挿入歌という感じだったろう)などを用いた変奏曲がたくさん書かれるようになったのはその顕れであろう。
実は、モーツァルトなどは拝借の常習犯だったふしがある。前にも書いたクレメンティのソナタと「魔笛」序曲との関係はわかりやすい実例である。モーツァルトはクレメンティのソナタを聴いて、
「ああもったいないもったいない。こんな面白い主題を、この程度にしか活かせないなんて」
と、居ても立ってもいられなくなったのに違いない。
「おれならこう展開するね。どうだ、聴いて驚け」
というわけで、「魔笛」が誕生したわけだが、モーツァルトにとってこれは唯一の例ではなかったはずである。たまたまこのケースでは、クレメンティの方も有名な作曲家だったから元ネタが残ったが、元ネタがすでに散逸してしまった有象無象の作品は、意外に多いのではないかと私は踏んでいる。大泥棒そこのけであろう。
「所詮真似は真似。オリジナルにかなうはずがない」
というのが現代人の感覚だろうが、案外そうとも言いきれないのが表現という行為の面白く、かつ非情なところで、魅力的なオリジナルの素材を作り出したとしても、それをうまく料理できるかどうかは保証されないのである。借用した素材ではるかにおいしい料理を産み出す者がいないと限ったものでもない。もとの素材の作者にとってははらわたが煮えくりかえるような想いではあろうが(だから前にも書いたが、クレメンティはのちに楽譜出版業を営んだのに、モーツァルトの作品はただのひとつも出さなかった)、後世に対してより益するのは、たとえ素材は借用でも完成品としてのクオリティが高い作品の方ではないだろうか。モーツァルトの存在がその何よりの証明である。ずっと後輩になるが、ラフマニノフなんかもかなり濃厚な容疑者とされる。
「三銃士」「モンテ・クリスト伯」など多くの血湧き肉躍る小説を書いたアレクサンドル・デュマだが、ある時、彼の作品が他人の剽窃ではないかという噂が立った。確かにデュマの作品は完全にオリジナルとは言い難く、元ネタがあるものが多い。
ある人が、ことの真偽を糾明すべく、デュマに訊ねた。
デュマは得意な顔で、
「そう、その通り。だが見てみろ。わしの書いたのの方が、ずっと面白いじゃろう」
……私の大好きなエピソードである。
もうひとつデュマのエピソードを。
彼の息子が、「椿姫」の原作を書いたデュマ・フィス(小デュマ。父と同じアレクサンドルという名前を継いだのでこう呼ばれる)で、「椿姫」は作者の実体験をもとに書かれたらしい。若い頃、ヒロインのマルグリット(オペラではヴィオレッタ)と同じような高級娼婦に恋をし、作中のアルマン青年(オペラではアルフレード)と同様、彼女と結婚したいのだがとおそるおそる親父に申し出た。作中の親父は心痛し、ヒロインに直接交渉して身を引かせることになっているが、現実の親父はフンと笑ってこう言った。
「やめとけやめとけ、あの女とならわしも寝たが、大した女じゃなかったぞ」
小説よりもずっと面白い反応だったと思うのだが、これは余談である。
ともあれデュマは、自分は超一流の料理人であるという誇りを持っていたのだ。素材などどこから拾ってきても大した問題ではないと思っていただろう。確かに、例えば神話や伝承をもとに想像力をふくらませて作品を仕上げる人は、ジャンルを問わず大勢いるわけで、この場合は決して盗用とは呼ばれない。その元ネタが同時代人の作品であったとしても、本質的に差はないのではあるまいか。
元ネタの作者が泣こうがわめこうが、完成品としての作品がよくできたものの方が人々に受け容れられ、後世に残ることになる。これはもう、どうしようもない現実なのである。もちろん、通説通り、
「真似はオリジナルにはかなわない」
という場合もあり、その場合はオリジナルの方が残るというだけのことで、要するに個別にしか言えるものではない。
元ネタをオリジナルよりもうまく扱える自信があるならば、堂々と盗め。それが私の意見である。それができるところが、表現活動というものの非情にして面白い点だと私は信じている。
著作権を守るというのは大事なことだが、表現活動のそういう部分を規制してしまうというデメリットもある。クレメンティとモーツァルトが今生きていれば、クレメンティはモーツァルトを訴え、昨今の様子を見るにおそらく勝訴するだろう。モーツァルトは賠償金の支払いを怖れて、「魔笛」序曲をああいう曲にはしなかっただろう。それは世の中にとって大いなる損失ではあるまいか。ましてや「無意識に似てしまった」ところまで問題にしては窮屈きわまりないことになる。
表現活動において、素材の盗用とか類似とかいう事柄は、どう考えても法律判断に馴染まないと思う。むしろ訴訟を起こした時点で、訴えた側は自分の作品が完成品として劣っていることを認めたと思われても仕方がないのではあるまいか。
著作権法が扱うべきは、あくまで作品全体であろう。他人の作品とまったく同じもの、あるいはどう見ても細部をちょっと補作したに過ぎない程度のものを、自分の「作品」として世に出したとすれば、それは文字通りの盗作であり、許されることではないが、あるフレーズが共通しているとか、出だしがそっくりだとかいう程度の「盗作」なのであれば、訴訟を起こすなどというのは表現者として恥ずべきことと思わなければならない(盗んだ方が、ではない)。
ただ、ひとつだけ私にも許せないケースがある。それは、無名の弟子の書いたものを、師匠が補作して(ひどい時にはそのまんま)師匠の名前で世に出すという行為である。今時まさかそんなことはしないだろうと思われるかもしれないが、江戸川乱歩などしょっちゅう他人に代作させていたそうだし、音楽畑でもまったくないとは言えない。
小説家志望の知人が、ある講座に参加し、講師の小説家に自作を読んで貰ったところ、
「そうねえ、この話、あたしの名前で持って行けば売れるかもしれないけどねえ」
と言われたそうだ。これはその小説家がひどい奴なのではない。知名度の高い作家の作品であれば読者はついてくるが、それと同水準だとしても、無名の作家となるとなかなか売れるものではないのだ。
その小説家は、自分の名前でその小説を編集者のところに持って行くなどということはもちろんしなかったが、やってしまう「先生」も居るかもしれない。「先生」の方も最初は悪気はなく、むしろ弟子の作品を少しでも世に広めようという気持ちがあるのかもしれないが、これだけはやってはいけないと思う。
あるいは時間に追われた「先生」が、素材だけ作ってあとは弟子や下請けにやらせるなどという場合。こういうことが日常化していたら、「先生」の名前は一種の「ブランド名」として解すべきかもしれず、最近「作曲家」ではなく「音楽プロデューサー」なる意味不明な肩書きを名乗る人間が増えてきたのはその反映かもしれない。
すでに世に出された作品の素材を盗むというのと違い、これらは本当の意味で、実際の作者から作品が奪われ、その人のものとしては失われてしまう。悪質な「盗用」であろう。
私自身、自分の曲の素材として例えばベートーヴェンを「引用」したことがある。私は「引用」と言っても、「盗作」と見なす人だって居るだろう。また直前に聴いた曲にかなり影響され、そっくりな雰囲気のフレーズが出てきてしまったこともある。これまた「盗作」と言う人も居るかもしれない。
「ここんとこ、×××みたいですね」
と演奏者に指摘されることも珍しくはない。たいていは一瞬の類似に過ぎないので、相手も冗談のつもりで言っているのだし、私も気にしたりはしない。
要するに全曲を貫くパトスがオリジナルでありさえすれば、それでよいのだと思っている。「引用」や「影響」や「一瞬の類似」の結果として、私に「独創性がない」「個性に欠ける」ことになるかどうかは、聴いた人が判断すべきことであって私の知ったことではない。断っておくが私の作ったものは、
──MICの曲だってことはすぐわかるね。
と言われることがわりに多い方である。
繰り返すが、自信があるのならどんどん盗むべきだ。盗まれた方も、法律に訴えるなどという野暮なことはやめて、賞賛あるいは挑戦と考えて奮起するべきである。盗まれるだけの魅力のある素材だったと考えればむしろ誇るべきだし、その素材を用いて「おれならこうする」とばかりに作られたのならば堂々挑戦を受けて立つ気概が欲しい。法律に訴えるのは表現者としての敗北に他ならないのである。
(2002.12.25.)
|