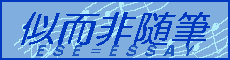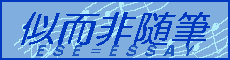|
私の手許に「Der Kanon」というドイツで出版された本があるが、つれづれに眺めていると実に面白い。タイトル通り、カノンばかり350曲以上も収録してある本だ。楽譜の現存する最古のカノンと言われる「Summer is icumen(夏は来たりぬ)」から、20世紀の作品まで、各時代を網羅的におさめている。
さしあたって、カノンとはなんぞやということを最初に説明しておかなければならない。
「蛙の歌」や「静かな湖畔で」といった、よく知られた曲で輪唱と呼ばれるものがある。いくつかのパートに別れて、同じメロディーを時間差をもって歌うというのが輪唱だが、これがカノンのもっとも初歩的な形と言える。つまりカノンとは、「特定の旋律を、複数のパートがさまざまな方法にもとづいて厳密に模倣しあうことによって作られる対位法的多声音楽」と定義づけられる。
この定義文ではわかりづらいかもしれないが、まず「特定の旋律を複数のパートが厳密に模倣しあう」というところは、輪唱を思い浮かべていただければすぐにイメージできるだろう。問題は「さまざまな方法」という点と「対位法的多声音楽」という点にある。
輪唱は、模倣の方法として「同一の音の高さ、同一の音価で」という条件がつく。専門的に言うと「等倍・同度の並行カノン」となる。
そうでないカノンもいろいろと存在する。ごくざっと説明してみよう。
等倍でないものとしては、拡大カノン、あるいは縮小カノンがある。最初に出るパートの音価を比例的に変化させる、つまり4分音符が2分音符になったり8分音符になったりするわけだ。音が長くなるのが拡大カノン、短くなるのが縮小カノンである。比例的というのは、4分音符を半分の8分音符に縮小するなら、もとの2分音符は、やはりその半分の4分音符で受けなければならないということだ。場合によっては同時に始まることがあり、そうすると拡大なのか縮小なのかはよくわからなくなる。
同度でないものというのは、ある決まった音程差をもって追いかける場合で、音程差により2度、3度……8度などと呼び分ける。バッハの「ゴールドベルク変奏曲」では、変奏3つごとにカノンが採り入れられていて、しかも第3変奏(1番目)は同度のカノン、第6変奏(2番目)は2度のカノン……という風に、第27変奏(9番目)の9度のカノンまで徐々に音程差を拡げてゆくという凝った作り方をしている。
ちなみに、
ドレミファ
という音階を考えると、ド−レ、レ−ミの間は全音だが、ミ−ファの間は半音になっている。これを例えば3度ずらして
ミファソラ
にすると、半音はいちばん下のミ−ファの間に来ることになる。同度や8度でない時、このように全音と半音が入れ替わることがあるのが普通だ。そうしないと調性が曖昧になり、うまく終われなくなってしまう。それでもなお全音半音まで厳密に模倣するのを厳格カノン、調性を優先させて全音半音の交代を黙認するのを定調カノンと呼ぶことにしよう。厳格カノンであれば、ドレミファを3度ずらせばミファ#ソ#ラということになる。
並行でないものとしては、反行と逆行がある。どう違うかというと、音の高さを逆転するのが反行カノン、時間的に逆転させるのが逆行カノンだ。こうなると、耳で聴いただけではわかりづらくなる。
ドミソファミレド
といったメロディーを考えてみよう。反行カノンは、このメロディーに対して、高い音は低く、低い音は高く答える。そしてその音程関係は保たれる。つまり、
ソミドレミファソ
となったり、あるいは
ドラファソラシド
となったりする。
並行カノン同様、音程差が生じるが、この場合、何度のカノンかということは一概には言いづらい。開始音の音程差とすることが多いが、そうすると最初に一音付け加えるだけで、あとは全く同じものが2度になったり3度になったりして合理的でない。
石桁真礼生さんの本では、「反転させる対称軸となる音が、その調の主音に対して何度音になるか」ということで定義しようと提起してあったが、これだと定義できない曲(『音楽の捧げもの』の終曲など)も出てくる。のみならず上記の「ゴールドベルク変奏曲」の中の第12変奏(4度のカノン)と第15変奏(5度のカノン)はそれぞれ反行カノンで書かれているのだが、石桁説に基づくとこれはどちらも3度の反行カノンということになり、期せずして石桁先生は大バッハに逆らうはめになってしまった。
私はそこで、「先行パートの主音を、後行パートが何度差で受けているか」という定義を考案した。これだと調性がある限り定義できない曲はなくなるし、「ゴールドベルク変奏曲」との整合性もある。
上に挙げた「音楽の捧げもの」終曲がなぜ石桁説で定義できないかというと、これは実は厳格反行カノンであるため、対称軸となる音が存在しないのである。一応ミですれ違っているようだが、半音の場所まで厳密に反転しているので、ドレミファソはソファミ♭レドと答えることになる。一般に厳格反行カノンは長調と短調が曖昧になることが多く、作るのは難しいが、この曲は見事にそれをクリアしている。
反行カノンにこだわりすぎたが、逆行カノンというのは例えば
ドミソファミレド
という音列があれば、それを逆から読んで
ドレミファソミド
と答える(紛らわしいのでよく見て下さい)。こうなるともう、耳で聴いているだけではさっぱりわからない。反行と逆行をうまく組み合わせると、ひとつの楽譜をテーブルに置き、それを両側からふたりの奏者がはさんで演奏するということもできるようになり、モーツァルトに作例がある。
同じように、拡大・縮小などと組み合わせることも可能になるし、もちろん音程差をつけることもできるわけだから、「厳密な模倣」という規則にがんじがらめに縛られているようなカノンも、結構ヴァラエティに富んだ広い世界を持っていると言える。
教科書にはこの他「逆比カノン」と言って、音の長さが逆比例関係になるような手法が載せられていることがあるが、実作に用いられた例を寡聞にして知らない。教科書に載っていた作例は、明らかに教科書のために試作されたとしか思えないものだった。実際にやってみるとわかるが、かなり無理があり、特に厳格な逆比にするのはまず不可能だ。
3声以上になると、片方のパートは並行、片方は反行という具合に作ることもできるが、作るのはむろんのことだんだん難しくなってゆく。
カノンの本には、これらのさまざまなタイプのものが載っているが、面白いのは、たいてい五線は1段だけで書かれているというところだ。最初に出るメロディーだけを記してある。それ以外のパートは、どういう具合に模倣するのかという指示だけついている。例えば反行カノンの場合だと、普通のト音記号に続けて、逆立ちしたト音記号が書いてあったりするのだ。こういうのを、実際に歌うために普通の譜面に起こしてゆく作業は、なんとなくパズルを解くような快感を覚える。
「Der Kanon」にはあまり意地悪な作品は載っていなかったが、時にはその種の指示がごく限られているものもあり、その場合はいろんな音楽的条件から模倣の仕方を割り出してゆかなければならない。こうなると完全にパズルで、「謎のカノン(カノン・エニグマータ)」とも呼ばれる。
どうしてそんな、わざわざわかりづらい譜面を作ったのか、ずっと不思議に思っていたが、最近なんとなく察せられるようになった。謎のカノンというのはかなり高度な知的ゲームなのである。18世紀頃までの即興演奏対決の話はこのエッセイの中でも何度か触れたが、同じように、片方が謎のカノンを出題して、それをもう片方が解いて演奏するというような対決もあったのではないか。
私はパズルも大好きなせいか、音楽を使ってこんな知的ゲームがおこなわれていた時代をとてもうらやましく思う。難問に頭を悩まし、解いてみれば美しい音楽になるのだから実に贅沢な遊びだ。
以上のさまざまな手法によりカノンが作られるわけだが、最後の条件がある。「対位法的」というところだ。
対位法というのは複数のメロディーを組み合わせるための規則のようなものだが、厳格に言い出すとかなりの禁止条項や制限事項が発生する。実際の楽曲では多少緩和されることもあるが、例えばふたつのメロディーの間で、同時にオクターブとか完全5度とかの音程差で動く、いわゆる連続8度、連続5度などはまず許されない。また、複数のメロディーがずっと同じリズムで動くなどということも避けなければならない。
カノンとして作られたものは、この対位法の規則を満たしている必要があるわけである。
カノンが好まれたのはなんと言ってもルネサンス期で、カノンだけによるミサ曲なども作られた。本にはパレストリーナによるカノン・ミサ「Missa ad Fugam」が載っている。キリエからアニュス・デイまで、ミサ曲の通常構成はすべて満たしている。
続くバロック期にもずいぶん作られた。それらを集大成したのがバッハの『音楽の捧げもの』というわけだ。
ただ、上記のような、きわめて拘束性の強い条件が課せられていたため、正面きった作品としては徐々に作られなくなった。バッハの時代、すでに下火になっていたようでもあり、それだからこそバッハは『音楽の捧げもの』で各種技法をカタログ的に網羅しておこうと考えたのではないかと思う。
バッハの時代、平均律の普及により、曲の途中での転調が自由にできるようになっていたが、カノンは残念ながら転調とは今ひとつ相性が悪いのである。追いかけてゆく方のパートが足枷になって、どうしてもひとつの調からそれほど遠ざかることができない。
独立した楽曲としてのカノンは、多くの転調を含む大規模な作品にはそぐわなくなっていたのだ。
また、そのあまりにパズル的な厳密さが、作曲家の自由な表現欲求に合致しなくなったとも言える。
かくして、カノンという形式そのものはバロック時代の終焉と共にほぼ重要性を失ったものの、廃れることはなかった。
実際、その後も多くの作曲家がカノンを作り続けている。さすがに正面きって作品でございますと称しているものは少なく、息抜きのような小品ばかりではあるが、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンもずいぶん作っている。さらにロマン派から、20世紀に至るまで、愛好者はあとを絶たない。作品としてはともかく、できるだけ厳しい条件で曲を作ってみるというのは、作曲家にとってはよい修業になるし、また頭の体操にもなる。上述したパズル的なところが好まれているとも言える。
シューマン、ブラームス、レーガー、フランクなどは、カノンの手法を作品中に巧みに採り入れている。フランクのヴァイオリンソナタ終楽章主題の長いカノンなど、実に楽しい。
さらに、シェーンベルクらが十二音技法を開発する時に参考にしたのが、まさにカノンの手法なのである。
十二音技法は、簡単に言うとまずオクターブに含まれる12の音(半音)を任意の順序で一列に並べ、その音列の順序に従って音を配置してゆくという作曲方法で、従ってある音、例えばファの音が鳴ると、残りの11の音が全部鳴り終わるまでは次のファは現れないという仕掛けになっている。だから12の音が平等に使われることになり、どの音が特に重要ということがなくなる。それまでの調性音楽というのは、主音、属音、下属音などといったように、音同士に序列が発生するシステムだったので、調性音楽からの脱却をめざしたシェーンベルクたちは、こうしていわば「音の民主主義」を図る方向でシステムを構築していったわけだ。
ところが、12の音をただ一通りの方法で並べただけでは、さすがに発展がない。
そこで、「移高(音列をそのままの形で高さをずらす)」「反行(音列の音程関係を反転させる)」「逆行(音列をうしろから読む)」「反逆行(反行と逆行のミックス)」といった音列のアレンジ方法を併用することにした。これをさまざまに組み合わせれば、変化に富んだ曲が作れる。うまく配置することによって、十二音技法を用いていながら調性音楽のように聞こえるという曲を作ることさえ不可能ではなく、この技法の提唱者のひとりであるベルクなどは実際にそういう曲を作った。
もうおわかりだろう。移高も反行も逆行も、各種カノンで用いられていたコンセプトに他ならない。
たまたま似てしまったという問題ではなく、シェーンベルクらは明らかに、カノンの手法を参考にして十二音技法を組み立てたのである。
この他にもメシアンらによるリズム・カノンのコンセプトがある。音程はいろいろに変化するが、リズムだけカノンになっているというものだ。
そんなわけで、カノンの考え方は現代にまで脈々と受け継がれているのである。
私自身も時々カノンを試作してみることがある。さまざまな規則を遵守しながら、なおかつ退屈でない曲を作るというのは確かに大変な作業だが、うまく行った時には、まさに難解なパズルを解き終えた時のような達成感を覚える。それをさらに「謎のカノン」のように書き直すのも面白い。誰かに解かせたいと思うが、そこまでカノンをわかってくれる人はなかなかいない。
合唱の演奏会で、ひとステージをまるまるカノンに宛てたことがある。聴客にはあらかじめ譜面を配って、説明をはさみながらいろいろなカノンを演奏してみた。いわゆるレクチャーコンサートの方式にしたわけである。その中で私の試作品も何曲か使わせて貰った。反行カノンと逆行カノンの作例である。また、
★バッハの4声の5度カノン「Pleni sunt coali」(4つのパートがそれぞれ5度ずつの音程差を持っているという手の込んだもの)
★ジョスカン・デ・プレの3声の拡大カノン「Agnus dei」(第2パートは第1パートの2倍、第3パートは第1パートの3倍、従って第3パートは第2パートの1倍半という長さの関係になるというややこしいもの。ちなみにそれぞれのパートには音程差もある)
★モーツァルトの4重カノン「Am Feuer zu singen」(4つの異なったメロディーがそれぞれ3声のカノンを形成する──というより、四部合唱がそのままカノンになって、結果的には12声合唱というとてつもないことになっている)
などを紹介した。それぞれ、歌詞をつけて歌った方が面白いのだが、とりあえずMIDIにしてみたのでお聴きください。そして、その精緻さに驚いてみましょう。 (2000.5.23.) |