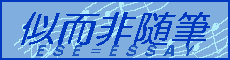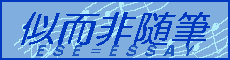|
ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキー(1840〜1893)は奇妙な作曲家である。ホモだったというのは有名な話であるが、私のいう奇妙というのはそういうことではない。ホモだのロリコンだのSMだのといったことは、芸術家と呼ばれる人々にとっては別に珍しいことではなく、もちろんそういう性癖のために彼らの作品が貶められているということもあり得ないのである。
チャイコフスキーの奇妙さは、これほど一般の音楽愛好家たちに広範な人気を保っている一方で、少し訳知り顔の人々にはまるで評価されないという、その落差の大きさにある。
おそらく作品のCDの売り上げでは、クラシック作曲家中でも屈指だろうと思われるのだが、音楽史の上で重要な存在として扱われることはあまりないのだ。
彼の位置付けは、ロシア国民楽派と西欧ロマン主義との折衷といったところで、折衷と言えば聞こえはいいが、要するにどちらから見ても中途半端だということだ。人気という点でははるかに及ばないムソルグスキーの方が、玄人筋の評価は歴然と高い。
かく言う私も、高校時代はチャイコフスキーを軽蔑し、「悲愴」が好きだという友人をミーハーな奴だとけなしていたものである。それが「玄人」たるものの当然の立場だと信じていたようだ。
大学に入ってから先生に、
「チャイコフスキーはね、映画音楽の元祖なんだよ。映画音楽でやってるようなことは、彼がみんなやっている。オーケストラの効果を勉強するにはいいね」
と言われ、そんなものかと思ったが、結局それだけのことではないかとも考え、その後はほとんど無関心になった。
チャイコフスキーに対する見方が変わったのは、卒業してしばらく後のことだった。
どこかの演奏会で「弦楽セレナード」を聴いて、不覚にも引き込まれてしまい、感動したのである。肌が粟立つような気さえした。
どうしてそんなに感動したのかと自分で振り返っているうちに、ふと思い当たった。
彼の曲は、すべてがツボにはまっているのである。ここで泣かせが欲しいと思うところには必ず泣かせが入る。盛り上がりたいと感じた時には、次の瞬間必ずわくわくするような盛り上がりが待っている。聴衆の期待が、ぴたりぴたりと、たなごころを指すかのように満たされてゆくのだ。チャイコフスキーの偉大さは、まさにこの点にあるのだと私は気づいた。
と共に、イアン・フレミングの言葉を思い出した。
――売れる本を書くのなんて簡単だ。読者が次のページをめくりたくなるように書きさえすればいい。
大ベストセラー「007」の作者のこの言葉は、そっくりチャイコフスキーの音楽にあてはまるのではないか。
あっ、と思った。
チャイコフスキーという作曲家は、小説家に喩えるなら、スタンダール、ユゴー、ゾラといった系列よりも、デュマ、ガボリオ、ルブランといった系列に属するひとなのではないか。日本で言えば、谷崎や太宰より、吉川英治や山岡荘八なのだ。いわゆる「正統」音楽史において継子扱いなのも、「一般」愛好家に大人気なのも、そう解釈すれば実によくわかるではないか。
われわれは、「クラシック音楽」という一枚看板に惑わされて、本当は全く別の評価軸で論ずべきものを、単一の価値観で見てしまうという誤りを犯しているのかもしれない。
他にもこんな例はありそうだ。折りにふれて考えてみようと思っている。
|